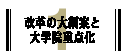
いま,日本の大学には,「改革の潮流」がひたひたと押し寄せています。戦後半世紀を経過し,まもなく21世紀を迎えるとき,大学教育の再構築, 研究水準の飛躍的向上,スタッフや施設などの教育・研究条件の抜本
的改善,教育・研究成果の点検・評価,組織の再編・整備,管理・運営の改善などの一連の「大学改革」が,それぞれの大学で真剣に模索され,実行に移されつつあります。
高校教育だけでなく,小・中学校教育,さらには子供の成長にまで大 きな影響を及ぼしている大学入試 のあり方の再検討が要請されるとともに,大学入学後も一部の学生に,低い学習意欲やキャンパスからの離脱,高留年率など大学教育への不適応現象がみられ,積極的に学習する学生にあっても,学習内容の細分化と総合的知識修得の弱さ,学習内容の高度化と修得レベルとのミスマッチが指摘され,学生全般の人間的成長の未熟さも次第に顕著になるなど,もはや看過することのできない教育問題が顕在化しつつあります。
また,情報化社会,国際化社会の到来のなかでますます高度な知識 を有する人材が求められているにも かかわらず,こうした人材の養成の任にあたる大学院の教育体制や施
設が依然として十分に整備されておらず,また,大学院生の生活の不安定性などから,人文・社会科学系 では修士課程への,自然科学系では博士課程への進学率が低迷しています。
さらに,研究レベルにおいても,人員・ 研究費・施設などが欧米に比較して劣っているなかで国際的に優れた 成果をあげている一方,学部・学科・講座等の組織の壁が
厚く,先端的・学際的・総合的研究の発展の要請に柔軟に対応で きない硬直性がみられ,また,人事の流動性の低さから,マンネリズムや甘えの雰囲気が発生しやすく,一部に研究の停滞が生じていることも否定できません。
こうした,戦後確立し半世紀近く稼働してきた高等教育システムの硬直化がもたらした 諸課題を正面からとらえ,新しいシステムづくりを模索しようというのが,いま全国的に進んでいる「大学改革」の背景です。


全国的なレベルでの「大学改革」 の潮流は,平成3年の文部省令の改正による「大学設置基準の大綱化・ 簡素化」が契機となって,一気に大きくなりました。
これは,学部教育などのカリキュラ ムや取得単位についての画一的な 規制を大幅に緩和し,大学の自主決 定に任せるというものでした。この規制緩和は,入学後1・2
年次前半の教養教育,2年次後半以降の専門教育という分離の壁を取り払い,さらに進んで教養教育を専ら担当する教官の組織である「教養部」の解体をもたらすことになりました。
さらに,平成3年度から開始された,大学院の整備・充実による教育・研究における「大学院重点化」の動きは,東京大学や京都大学をはじめとする基幹的国立大学を席巻していきました。
九州大学では,こうした全国的な潮流と時を同じくして,「大学改革」 を推進するもう一つの強い渦流が生じました。
平成3年10月に,福岡市西区元岡・桑原等地区を移転候補地とする「九州大学新キャンパス移転構想」が 評議会で承認されたのです。当然,新しいキャンパスは全面的な
「大学改革」を空間的に実現するものとして構想されなければなりません。全国的な改革の流れと歩調を一にする「九州大学の改革」ではなく,移転のタイムスケジュールに合わせ,かつ新設されるキャンパスが長期間使用されることから長いタイムスパンを見据えるとともに,教育・研究,管理・運営,社会との連携など全分野にわたる改革を要請されることになりました。
九州大学はこうした要請に対応して,平成4年6月に「九州大学における大学改革の基本構想」を評議会で審議・承認するとともに,翌5年6月に,学部長・
研究科長・研究所長など部局長によって構成される将来計画小委員会のもとに改革のあり方を検討する 専門委員会を作り,約2年の議論を経て,平成7年3月に「九州大学の改革の大綱案」,5月に「続・九州大学の改革の大綱案」を評議会で承認しました。
「大綱案」は,「国際的・先端的研究教育拠点(COE :Center of Excellence )の形成」と「自律的に変革し,活力を維持し続ける社会に開かれた大学の構築」の二つを基本的なコンセプトとし,その実現のために「組織の再編・整備」「教育・
研究の改革」「管理・運営の強化」 の三つの側面から多面的な改革案を提示しました。なかでも,「全学の大学院の重点化」と「研究院制度」の導入は,改革の中核的位置を占めていました。
「九州大学の改革の大綱案」は,大学が自ら策定した改革の長期計画で,こうした長期計画の策定は全国の国立大学でも余り例を見ない 先駆的なものです。それだけ「移転」が全面的かつ迅速な「改革」の推
進を要請したとみることもできます。
「大学院重点化」とは,「研究科」の専攻を新しい時代に対応して再編・充実するとともに,学生定員を見直し,従来「学部」にあった教官の所属 組織である「講座」を大学院に移すことにより,大学院の重点的整備
を行うものです。
九州大学の大学院重点化は,平成9年4月の医学系と工学の各研究 科から開始され,その後,理学,生物資源環境科学,法学,薬学,人文科学,経済学,歯学の各研究科が続き,平成12
年4月に「全学大学院重点化」 が完了して研究大学としての全容が整いました。
また,「大綱案」が承認される前から,全国的な改革の潮流と歩調を合わせる形で,教養部の廃止と大学教育 研究センターの設置,数理学研究科 及び比較社会文化研究科の学部を
基礎としない大学院の独立研究科が設置されました(平成6年度)。この独立研究科設置の動きは,「大綱案」承認後一層加速され,システム 情報科学研究科(平成8
年度)と人間環境学研究科(平成10年度)が相次いで設置されました。このうち人間環境学研究科は,教育学,人間科学,建築学といった人文科学と自然科学が融合する学際研究科として全国的に注目されました。また,九州大学最初の独立研究科である総合理工学研究科(昭和54年度設置)も,大幅に再編・整備されました(平成10年度)。
