◎シリーズ九大人

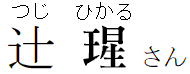
ヨーロッパ、ドイツから見た日本と九州大学
辻先生はこれまで、ミュンヘン大学と九州大学との橋渡しをしてくださると同時に、特に国際交流に関してのアドバイスや講演、二十一世紀プログラム学生との対談など、様々な形で九州大学にご助力くださいました。また平成十六年四月からは、九州大学ミュンヘンオフィスのディレクターとしての活動も期待されています。
昨年九月末、来学された際に、お話をうかがいました。
 Q…
Q…
先生は「カフカの研究家」ということでよろしいのでしょうか。
辻…
私にとってカフカは、最も親近感を抱かせてくれる作家です。日本でもカフカの名前がよく出てくるようですが、結婚式や葬式では、ゲーテは引用されてもカフカが引用されることはありません。カフカの作品には、私たちの日常生活とは異なった現実が存在しており、読んでいると、どちらが本当か分からなくなってきます。でも、あまり知られていませんが、カフカは笑い上戸でした。実は私も笑い上戸で、時折、とても困っています。
Q…
本日は、「ヨーロッパ、ドイツから見た日本と九州大学」というテーマでお伺いしたいと思います。
辻…
率直に申し上げて、九州大学はミュンヘン大学内ではほとんど知られていません。存在していないと考えた方がいいかもしれません。ドイツでは少数の人しか日本についての詳しい知識を持っていないのです。もちろん学長周辺と留学生課は別です。
多くのドイツ人が日本について知っているのは、第二次世界大戦で同盟国だったとか、バブル経済の時に脅威を感じさせられたというようなことで、親近感は抱いてくれていても、知識が具体的ではありません。しかし、日本語を学ぼうとする学生は少なくない。なぜかはよく分かりませんが、マンガと寿司と映画ばかりでなく、日本の古典的な文化にも関心を持っており、結局のところ、それらを統合している感受性豊かな活力そのものに惹かれているらしいのです。無意識的なものですが、とても参考になる事態です。ミュンヘン大学と九州大学との関係構築も、根本的には、こうした活力に基盤を見いだしていかないといけないと思います。でもこれは、今の学生たちに視点をおいた見方です。先生方の場合には、少し話が別です。
九州大学から来られる皆さんは
目つきが穏やかで、ゆったり構えています。
Q…
それではミュンヘン大学、そして欧米の大学や国と付き合っていこうとする場合、九州大学は、どうあるべきだとお考えでしょうか。
辻…
まず、ヨーロッパ流の交渉には不慣れであるとしても、ミュンヘン大学と接触する皆さん個人個人が、一方では外交官であるという意識を持たないと、うまく交渉ができないでしょう。
九州大学からミュンヘンに来られる先生方や博士コースの学生さんたちは、皆さん目つきが穏やかで、ゆったり構えておられます。九州は食べ物がおいしく、気候温暖で、自然が豊かなためでしょうか。ところが、東京大学に行きますと、みんなが、むつかしい目つきをして、焦っているように感じられます。とにかく、だいぶ感じが違います。大学の先生には皆そういう傾向がありますが、九州大学の先生方は特に内向的な活動をこれまでやってこられており、法人化後も、これから先どうなるか暫く様子を見ていよう、とお考えなのではないでしょうか。しかし、競争にさらされているところは、もっと焦っているように感じられます。
法人化によって、今行っていることの意味を問われながら、新しいものを出していかなければならなくなりました。研究をただ進めるのでなく、その研究の社会的意義を同時に喧伝していかなければならない。そこのところを九州大学の先生方が本当に理解しておられるか、ちょっと心配です。立派な研究をしていても、それを世の中に訴える力や、それを正当化してみせる社会的な配慮が求められています。研究の社会的な意義を、国際的にも知らせてみせる必要があるのです。また、そのための日常的な国際交流も必要になりました。欧米人は常に自分の業績を正当化しようとしており、そのような自己主張をしあう中で友人を作っていきます。そして、嘘をついてもその人と助け合うというのが友情です。与えられた社会が、もともとセチガライのです。やさしく、うるわしくしたまま、協調していけるような世界ではありません。
Q…
九州大学が将来構想の基本的方向として標榜する「アジア指向」については、いかがお考えでしょうか。
辻…
欧米指向から解放された目で見れば、各国の特殊性を受け止めようとする実際的態度が当然出てきます。「アジア指向」を、概念的で静的なものにしてはいけません。身近な問題として積極的に関与する動的な姿勢から出発しないといけないと思います。自らの行動を社会に対して正当化しようとする立場があれば、当然、具体的に何をどうするかがテーマになってくる筈です。範囲や立脚点ばかり気にしているのは、動かないでいるための口実づくりです。アジア指向も、現実的な手を次々に打ってみて、よさそうだと思ったら、サッと事を進めなければいけません。のんびりと、どうしようかなと考えていたら、それだけで遅れをとってしまう。
欧米にもそういうのんびりした面がないわけではありません。しかし彼等には独特の利己的なバイタリティーがあって、スマートに礼儀を尽くしながら、チャンスを捉えて具体的な行動に出ていきます。日本は、なかなかそれができない。九州大学にも、執行部の方々が焦らざるを得ない、そういう土壌があるのではないかと思います。しかしまた、焦ると浮いてしまう、というのも、もう一方の大きな人間的な現実です。
|
強力に学問的な成果に結実させようというのが 九州大学のアジア指向であれば、もちろん○(マル)です。 | |
 | 
|
| 総長室で梶山総長(左)と語る | 大学の行事などが行われる ミュンヘン大学ホールの入口 |
Q…
九州大学のアジア指向には、「歴史的・地理的な必然が導く」という説明がついています。一九一一年の九州帝国大学創設時には既に朝鮮からの留学生を受け入れていましたし、現在いる留学生千百名余りの八割以上がアジアからの学生です。
辻…
留学生受け入れについては、優秀な研究者を育てることと、社会人となる一般学生を多く受け入れることとを、分けて考えたほうがいいと思います。しかし、いずれにしても、その入口で失望感を与えてしまうと取り返しがつかないことになる。その意味で、大学が日本語教員をどう考えているかは大切です。日本語の先生方が、留学生を受けとめる最前線にいる方々だからです。
ミュンヘン大学の学生は約四万八千人で、女子の割合のほうが少し高く、男子は兵役や社会奉仕の義務などがあって、年齢も日本人学生より上の者が多い。授業料は要りませんが、大体がアルバイトなどで半ば自活しており、義務としてのインターンシップ制度もあって、彼等は社会的に大人です。そのような学生が、日本で学びたいと希望して来日してくるわけです。その学生の日本語能力だけでなく、知的水準や創造力を推察して、知性を喚起しながら教えていただきたいと思います。日本語の授業や当初の日本での生活で、インテリジェンスのある学生を失望させるようなことがあってはいけない。そういうことがあると大きな損失です。これはミュンヘン大学の場合でも、一番難しい、一番気になる問題です。学問をするためだけに、外国語を習わなければならないのだったら、どんな外国語だっていやになってしまう。外国語なんて、もともとそんなにできるようになるものではありません。外国語を好きにならせることが必要なのです。そして、好きになるとは、外国語を通じて新しいものの見方に出会い、そこに喜びを感じられるということです。教師はそのための機関です。
 Q…
Q…
学生受け入れに関しても、国際交流は本気でやるべきことだと。
辻…
どうせ欧米とは関係を持たなければならないのだから、アジアも忘れていませんよ、と声高に言っておこうというのが九州大学のアジア指向なら×です。アジア指向は、自己指向であり、人間指向です。これを、強力に学問的な成果に結実させようというのが九州大学のアジア指向であれば、もちろん○です。
研究する分野が何であれ、研究の対象は、自分達が見過ごしてしまっている現実の中にあるはずです。その意識が重要なのであって、二つの国の大学が共同研究をするのは、二つの国自身を対象にした研究でもあるわけです。例えば二つの大学が、同じ講義題目を立てて、それぞれでその講義を行なっていけば、それぞれの国自身が、研究対象にならざるを得ません。ミュンヘンと九州でこうした流れを作り、そこにアジアのいくつかの大学を共同研究者として入れ込んでいく、というようなことも、一つの重要な方法だと思います。何とかして、ちょっと不馴れなところにも踏み出していただきたいな、というのが九州大学に対する私の切実な願望です。