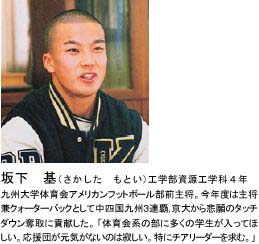
大学が与えてくれるのは,4年間何かをする器だけ。
部活をやって初めて学べること,
感じることのできる喜びがあります。
柴田副学長:今日は時間を割いてお集まりいただいて,ありがとう。
社会が変わると大学も変わらなければならないと言われます。果たしてそうでしょうか。一理はありますが,私はむしろ大学が社会を正しい方向に導いていくのが本来の姿であると思います。今は個々の利益が公の利益に優先する風潮が見られますが,社会全体のことを考える教養人,社会の色々なところで活躍し社会をそして世界をいい方向に導くことのできる人材を,どれだけ育てられるか,それは大学の重要な役割であると思います。
今日は,九州大学がそのような人材を育てるためにどうあるべきかを含めて,九大生である皆さんの普段感じていることや意見を聞かせていただきたい。
ではまずお一人お一人に,九大への思いを含めて自己紹介をしていただきましょうか。
池田:私は今年度から始まったAO,つまりアドミッション・オフィス方式選抜で九大に入りました。法学部を選んだのは,司法試験に合格して弁護士になろうと思ったからですが,現在は,今でしかできないことがあるのではと考え,九大生協の活動をしています。1年間は司法試験のための専門学校などへは行かず,これからの自分にプラスになり,見聞を広められるような活動をしたいと思っています。「アイデアメニュー・コンテスト」というのをご存じでしょうか。組合員から献立のアイデアを募集し,当選作は暫く生協のメニューとしてお出しする企画です。組合員の交流の場としてのこの企画の成功が,今一番興味あることです。
坂下:私は工学部の物質科学工学科の1年生ですが,九州大学も物質科学も私の第一志望ではなかったのです。でも入ってみて,1年生から少人数による研究があり,こんな研究もあるのかという発見があって,今は進みたいコースも見つかりました。
共通教育科目では,工学系より文系の授業が面白く,専門に進む2年前期までの,このような授業が存分に取れる間を大切にして,視野を広げたいと思っています。
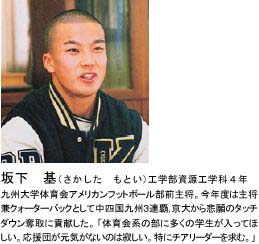 |
大学は待っているだけでは何も与えてくれない。 大学が与えてくれるのは,4年間何かをする器だけ。 部活をやって初めて学べること, 感じることのできる喜びがあります。 |
柴田副学長:私の4年間は勉強2番目,部活動が1番でした。九大の工学部に入学した動機はあやふやでしたが,スポーツが好きだったのでたまたまアメリカンフットボール部に入り4年間がんばってきました。自分としては満足していて,最高に楽しい4年間でした。
九大に求めるものというのは特にありません。アメフトに入るとき先輩に「大学は待っているだけでは何も与えてくれない。大学が与えてくれるのは,4年間何かをする器だけだよ。」と言われましたが,そのとおりだと思います。4年間で何ができるかは,その人次第だと思います。
阿部:あなた方の努力が実りつつあり,アメフト部は中四国九州で3連覇して,先日は京大から初のタッチダウンを奪う健闘を見せました。20世紀中に点が入ってよかった,ありがとう(笑)。
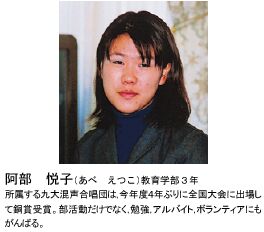 |
やる気さえあれば, いろんな体験ができます。 |
柴田副学長:私も混声合唱団での活動に没頭して過ごしています。入学したとき,大学は自由なところだから自分のやりたいことをやろうと考え,多くの人と出会えるようにサークルに入りました。混声合唱団を選んだのは音楽が好きだったのと雰囲気が明るかったからです。ここ4年間は全国大会出場を逃してきたのですが,今年は「みんなの絆を深めよう」をスローガンに1年間がんばって,全国大会に出ることができてうれしかったです。そしてそれ以上に,サークルを通していろいろな人と出会えたこと,人とふれあうことの大切さを学んだことを有り難く思っています。
大学に求めるものということですが,大学というのは自由な活動の場を提供してくれるだけで,学生が何かを求め,活動を通して何かをつかみ取って出ていくところだと思います。
新井:坂下さんと阿部さんには,クラブ活動という人との交わりのなかで得たものの大きさを語ってもらいましたが,一人,自主研究でがんばってきた新井さんの4年間はどうでしたか。
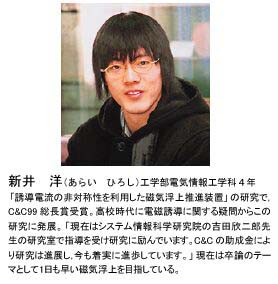 |
柴田副学長:私は16歳のときに考案したシステムについての研究を続けてきました。大学では1年のときに C&Cという学生の自主研究を支援するプロジェクトができ(解説①) ,それに応募して助成を受けることができたおかげで研究も進展しました。その点,九大に入学して良かったと感じています。恐らく他の大学にはこのような制度はないでしょう。私は他の大学の受験に失敗して浪人生活も経験しましたが,あの時にそのような大学に入学していたらと考えると背筋がぞっとしてきます。
私も坂下さんと同様,大学の勉強は2番目ですね。杉岡総長と柴田副学長へのお願いですが,ただテストの点がいいというのでなく,本当に学問に熱心な,大学で本当に有意義な生活を送ることができるようなシステムを作っていただけないでしょうか。例えば、一般的な小論文でなく,大学でどのような研究をしたいか,そのために現在このようなアイディアを持っていて,これまでに自主的にこのような研究をしてきたというような,いわば入学論文のようなものを課して選考するのも良いのではないかと考えます。
杉岡総長:この4月から始まる「21世紀プログラム」というのは,まさにそういう学生を取りたいと思って始めました。4年間自分が追求したいことをやれる,そういう体制を取っています。ぜひ多くの学生に参加してもらいたいと願っています。
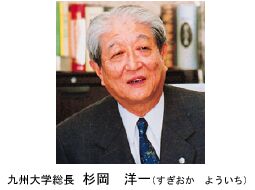 |
大学は自分で求め, 自らを向上させる場です。 文系は理系のことを 理系は文系のことを できるだけ多く学んでほしい。 |
柴田副学長:好きなことをやれるということは,向学心がないと何もできないということです。大学は自分で求め,自らを向上させる場ですから。また,そんな気持ちを持っている学生のやる気を失わせる大学では困ります。
ウォーカー:ウォーカーさんの「カルチャー・カフェ」もC&Cで採択されたプロジェクトで,かなり定着してきたようですね。私も何回か寄ってコーヒーをいただきました。
杉岡総長:私は留学生として日本に来て4年になります。九大に来る前は,1年間交換留学生として東京にいました。九大は以前いた大学などと比べ,より自由にやりたいことができるという印象です。カルチャー・カフェもC&Cによる援助のおかげでうまくいっています。
九大に来た最初の1年間は国際交流会館に住んで,大学までの往復約1時間を自転車で通っていました。会館には外国人しか住んでいませんし,最初の半年は留学生センター内で日本語の勉強だけ。日本での貴重な時間なのに日本人との出会いが少なく,少し憂鬱でした。専攻が環境心理学なので,日本人学生と留学生の出会いを進めるためにはどういう環境を作ればいいか考えているとき,C&C があることを知り応募しました。留学生センター前に作ったカルチー・カフェという喫茶店を核に,交流を少しずつでも広げていければと思います。
柴田副学長:おっしゃるように,留学生だけのドミトリーに住むというのはいけないと思います。留学生と日本人学生とが一緒に住める宿舎をと思っているのですが,日本人学生寮の施設改良を要したりで実現していません。新キャンパスの寮は,是非一緒に住めるものをと計画しています。
ウォーカー:今,日本人学生,留学生ともに自由に来て交流できる場所として「学生交流プラザ」という施設を計画しています。できたときは,カルチャー・カフェ2 号店を出してくださいよ(笑)。
柴田副学長:是非,よろしくおねがいします(笑)。
南波:南波さんは派遣留学生(解説②)として1年間アメリカで学ばれたわけですが,九大へ戻って来られて印象は如何ですか。
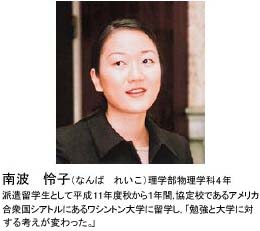 |
アメリカに行って発見したことは, 勉強ってこんなに面白かったんだと いうことです。 |
杉岡総長:私が留学したのはシアトルのワシントン大学です。留学する前は,みんなどうしてこう覇気がないんだろう,どうして大学は私の求めているものを与えてくれないんだろうと思っていたのですが,留学して大学に対する考え方がかなり変わりました。
アメリカに行って発見したことは,勉強ってこんなに面白かったんだということです。これまでは,いい成績を取るためなど,外的要因によって机に向かっていたような気がします。それがアメリカに行って,頼りになるアドバイザー制度や,いつでも利用できる充実した図書館など,勉強したいと思えば存分に勉強できる環境の中で,自分が学びたいと思うものが見つかりました。そして,学ぶことの楽しさ,知識を吸収し頭脳を刺激することのおもしろさに気づいて初めて大学の有り難さ,おもしろさが分かりました。
そういう向学心を持つ学生の受け入れ体制という点で,アメリカの大学に比べると九大はもうちょっとかなという気はします。ただ,勉強は一人でできることであって,そのおもしろさにいかに気づくかは本人の問題です。大学はそういうおもしろさに気づく手助けをしてあげられることが大切なのだと思います。視野を広げるための,自分の適性を見つけるための教育機関としての役割です。
南波:向こうでは何を勉強しましたか。
杉岡総長:私は物理学科の学生ですが,向こうでは取りたい授業を誰でも取ることができるので,文科系の授業をできるだけ多く取りました。その中でビジネス・ファイナンスの授業が本当に面白かったのです。物理とは直接関係がないのでちょっと困っていますが。
南波:私の頃は文系,理系と大きな枠で入学し,専門を考えるのはそれからでもよかった。今はもっと狭く,学科単位で入学する場合もありますね。
杉岡総長:高校生で進路を決める必要があるわけですが,それはちょっと無理があるかもしれません。
柴田副学長:大学に入ってからも道を変えることのできる幅があるといいのでしょうが。それともう一つ,向こうではオフィス・アワーに自由に教官に会いに行ってアドバイスを受けられますね。九大でも,皆さんは先生とそういう接し方をしていますか?
杉岡総長:六本松にブラウジングルームという,そういうアドバイスを受けるための部屋があります。利用していますか。
柴田副学長:特定の部屋へ行くのでなく,どの先生にでも相談し指導を受けることができるというのがいいのでしょうが。
原:先生が研究第一の方であったりすると,勉学上の悩みについてのアドバイスを受けるというのは難しい場合もあるかもしれません。でも,意欲に満ちた学生に育てることは,取りも直さず,我々に続く人材を育てることでもあるわけですから,我々教官は,もっとそういうことに熱心でなければならないと思っています。その辺,韓国語学研修(解説③)に参加した原さんは如何ですか。
柴田副学長:私は学部までは他の大学にいて,朝鮮史を勉強するために九大の大学院を選びました。九大にはそういう私のような学生に対する受け皿があると思います。特に私の参加した韓国語学研修はとてもいい制度だと思います。また九州史学会でも韓国の有名な先生方を招いてすばらしい発表を聞くことができましたし,昔からの本の蓄積があり,また新しい本も入るので,さすが九大だなと思っています。
原:原さんの参加された語学研修は,杉岡総長が韓国に直談判に行かれて成った制度です。日頃学生からあまり誉められることがなく,あれやこれや早急に改善しなければという強迫観念にさいなまれている私としては,誉めていただくとうれしいですね(笑)。他の大学から来て,九大生の印象は如何ですか。
柴田副学長:学生は非常に高い能力を持った人がたくさんいますが,全体にのんびりしていてもったいない気がします。その気になりさえすれば,色々な機会や手段が準備されているのですから。
杉岡総長:求めるものが明らかなら,九州大学にはそれを与えられる環境があると思うのですが,そこに気づいてもらえていないのではないでしょうか。我々が,情報提供の努力不足を反省しなければならないことでもあります。
例えば「九大広報」です。学外では地元自治体や経済界,九州山口の主な高校,そしてOBの方々にも読んでいただいています。これには九大生向けの記事,例えば皆さんが利用できる様々な制度など も絶えず掲載していますが,残念ながら十分に読んでもらえてはいないようです。多くの九大生に色々な情報を活用してほしいし,自分の通う大学について知り,大学に対する意見も出してほしいと思うのです。
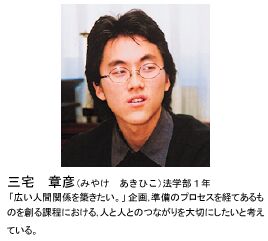 |
南波:学部の棚に並んでいるときは,表紙の上半分,「九大広報」と書いてある部分しか見えないんです。学生が興味を持ちそうな記事やキャッチフレーズを上の方に書いたらいいと思います。それに「九大広報」ではちょっとむつかしそうな印象を受けます。
坂下:読んでみると結構おもしろい。でもレイアウトが学生向きではないかもしれません。
三宅:表紙の写真に学生を載せてください。
学生にアピールするカラフルなポスターなどを掲示板に貼ってはいかがでしょうか。目につかないことには,認知されないと思います。
三宅:ありがとう。参考にさせていただきます。もう一つ,心配なことがあります。最近,体育系の部活動を敬遠する傾向がありませんか。だとしたら残念なことだと思います。私は学生時代バレー部で,挫折に耐える気力やフェアプレーの精神,人とのふれ合いなど貴重な体験ができたと思っています。その意味で,学生時代にスポーツをやることは大事だと思うのです。
坂下:体育系の部活動だと,まず時間的に拘束されるという印象があります。高校の部活ではある程度拘束されたので,大学ではあまり拘束されず自由にやりたいという人が多いようです。
杉岡総長:アメフトは週5日練習しています。それは目標を達成したいから,やりたいからやっているのです。でも1年生には,まず「週5日」が目に付くようです。私が1年生の時は部員が80人いましたが,今は約半分になりました。部員確保は,私たちの目標達成のためには重要課題です。
池田:練習を強制されるイメージばかりでは困りますね。部活動の練習は大変ですが,そこから広がっていくものや得られるものは,学生時代ならではの貴重な財産になります。
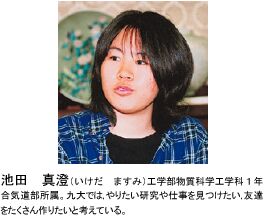 |
南波:受験に追われる高校時代に,部活は時間にしばられるというイメージができあがってしまうのではないでしょうか。
杉岡総長:私は高校時代は体育系の部活をやっていました。いい思い出もあるのですが,時間の拘束や怒られたことなどのネガティブな印象も残っていて,大学に入ったら自分のために時間を使おうと思いました。
坂下:大学での部活動は,大人として自発的に行うものです。それが高校時代とはちょっと違いますね。
池田:アメフトには後援会があって,私たちが存分にアメフトに打ち込めるのも,その方々が動いてくださるおかげです。まわりの人たちに支えられていることの有り難さを感じると同時に,社会もそういうふうに成り立っているのだと思うようになりました。これはアメフトをやって学んだことです。部活をやって初めて学べること,感じることのできる喜びがあります。後輩たちにはぜひ部活動をやってほしいと思います。
阿部:でも大学に入学したとき,部活だけでなく,アルバイトもしたい,遊びも勉強もしたいと,そういう気持ちがあります。
柴田副学長:混声合唱団も週3回,2時間半の練習があります。また月1回は土曜日も練習でつぶれます。でも私は部活のほかにアルバイトも,勉強も,ボランティア活動もしました。やろうと思えばやれないことはありません。合唱をやっていて,他大学のサークルとの交流も大きな楽しみでした。また演奏会を開催するために,大学外の色々な方々と交渉しなければならなかったりして,社会勉強にもなりました。やる気さえあれば,いろんな体験ができます。
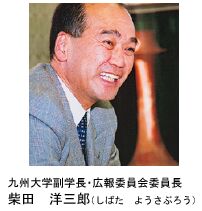 |
色々なことをやりたい気持ちは 大切ですが,広く浅くやるのと同時 に何か一つ深くやることも大切です。 |
阿部:色々なことをやりたい気持ちは大切ですが,広く浅くやるのと同時に何か一つ深くやることも大切です。サークル活動はそのいい例だと思います。アメリカの学生はその両方をやっていると感じます。この深みが,ほかのところで役に立つのです。合唱の全国大会は札幌で開催されたと伺いましたが,参加費用はどうしたのですか。
柴田副学長:自費で参加しました。その前の九州大会は沖縄でしたので,苦労しました。経費的なことから参加を見合わせた部員もいます。
杉岡総長:それは,旅費だけでも大変でしたね。部活動への資金的援助は,今は皆さんの活動が広がってうまく対応できていません。例えば全国大会に出場するような部やサークルには資金援助できるような仕組みが作れないかと思っています。
柴田副学長:今,教職員や同窓の方々に創立に向けた募金をお願いしている後援会ができると,そういう援助も可能になるのでしょうが。
施設についても,全ての部やサークルが存分に使えるようになるといいのですが,移転を控えた今は増設も難しく,気の毒だと感じています。新キャンパスではアメリカにも負けない施設をと考えていますが,今は限界がある中でうまく使っていただきたいと思います。
杉岡総長:新キャンパスでは空気浮上式リニアバスを走らせるような報道がなされていました。私の磁気浮上装置も役立てればいいなと思います。
柴田副学長:新キャンパスは,交通やエネルギー,廃棄物処理など先進的な技術も取り入れて,未来都市が見えるようなものにしたいと考えています。交通システムは新聞に出たもののほかに,工学部でも研究が進んでいます。あなたのアイデアも含めて,新キャンパスでの実用化に期待しています。九州大学は新キャンパスで大きな飛躍を遂げようとしているわけですが,そのためにも現在の九大がどうあるかが大事です。今の九大を,あなた方が入ってよかったと思える九大にしたいと思っています。
杉岡総長:現在でも,九大の学生が利用できる大学の資源は相当なものがあります。それをみんなに伝えたいのです。例えば南波さんや原さんが参加した留学制度,新井さんの研究やウォーカーさんのプロジェクトを助成しているC&Cなどたくさんあるのに,気づいてもらえない。こちらのPR下手は自覚していますが,残念な気がします。
阿部:国際人となるためには,まずは英語をはじめ外国語ができないといけません。言語文化研究院の箱崎分室は利用していますか。
柴田副学長:2年生のとき利用しました。
杉岡総長:行った人には,その良さが分かってもらえます。
三宅:今,ネイティブの先生が学内に大勢いらっしゃいますが,積極的に利用してほしいと思います。1 年生の語学の講義はどうですか。
杉岡総長:ネイティブの先生から「自分の言葉で書きなさい」と言われ,自分の意見を英語で書く訓練ができて面白いと思いました。講義の中で英語でディスカッションしたり,ディベイトをする機会があればいいと思います。
南波:外国語ができる前に,まず日本語で自分の考えをきちんと表現できないといけない。流ちょうであるよりもまず話す内容が大事で,内容のあるしっかりした考えを十分に相手に伝える訓練が必要ですね。
ウォーカー:どう話すかよりも何を話すかが大事だと,アメリカでつくづく思いました。まず話す内容についての蓄積がないと。私はアメリカで,もっと日本について勉強しておけばよかったと思ったものです。
三宅:アメリカでは毎日のようにディスカッションがあります。それに外国語の授業も毎日,集中的にあってなんとか使えるようになります。週2回ではちょっと足りないと思います。
柴田副学長:同じタイプの講義を,ある時期集中的に,例えば週に4,5日講義があるという形でやることは難しいでしょうか。
杉岡総長:セメスター制のことですね。夏休みの集中講義など,一部の語学科目などではすでに実施されています。
三宅:来年度から始まる21世紀プログラムでは,高い語学力の修得が一つの要件となります。
柴田副学長:21世紀プログラムの学生は,どの学部のどの講義も取れると聞いていますが。
杉岡総長:何を目指すかによって,取りたい科目をオーダーメイドできるというのが21世紀プログラムです。しかし,21世紀プログラム生だけでなく,すべての学生さんが,すでに総合選択履習制度によって,どの学部の講義も取ることができます。
柴田副学長:あることの専門家である前に,豊かな教養を備えている必要があります。ロー・スクールはそういう発想でしょう。予備校などで司法試験のための受験勉強ばかりしていて立派な弁護士や裁判官になれるか。その前に社会のことを知り,教養も豊かでないといけないという考え方です。ハーバード大のロースクール入学の要件は,法律の専門知識ではなく,法律以外の知識・教養の高いことが求められると聞いています。文系は理系のことを理系は文系のことをできるだけ多く学んでほしい,そういうフィロソフィーが必要だと思います。
新井:研究や部活に打ち込んだ人たちは,深い部分と広い部分をどう両立させましたか。
坂下:選択の余地なく機械的に取った講義は,やはりうまくいきませんでした。
杉岡総長:自分で取りたい科目でないと,モノになりませんね。専門の科目でも,授業で最初からいきなり知らない用語を使う先生がいて,分からないままドンドン進んで,なお分からなくなって眠くなる。そういう悪循環に陥った科目がありました。
分からないときは,すぐ「分からない」と訊けないのですか。アメリカではその辺どうでしたか。
| 休講が多いですね。 アメリカでは許されません。 でも,こっちでは学生が喜んでいる。 |
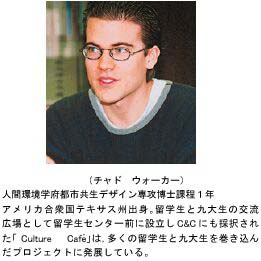 |
杉岡総長:自由にどんどん質問します。
柴田副学長:そういう雰囲気の授業でありたいですね。
杉岡総長:授業に対する注文は,遠慮なく先生やアドバイザーなどに申し出てください。
ウォーカー:皆さんは,月謝を納めているんだから,分かるまで尋ねる権利がありますよ。
南波:休講が多いですね。アメリカでは許されません。でも,こっちでは学生が喜んでいる。
杉岡総長:面白くなかったり,分からない授業でも,私は受けることはムダではないと思います。1年後にふとしたことで分かったり,ほかのこととつながったりすることがあります。それは,なかなか楽しい経験ですよ。
南波:アメリカの授業のどこが九大のそれと一番違うと思いましたか。
杉岡総長:アメリカでは基礎から積み上げ積み上げ教えてくれる点でしょうか。日本では,高度で専門的なレベルで教えて,ここへ上って来いと。やる気のある学生ならがんばってそこまで行くのでしょうが,その逆は多いと思います。
ただ話を聞かせるだけでなく,学生が自然と学びたくなるように仕向ける教育ですね。1 年生の授業でアンケートは取られていますか。
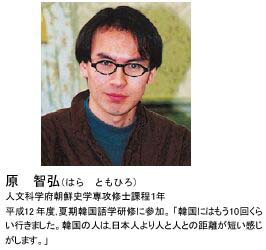 |
杉岡総長:学期の最後に行われます。
池田:もっと前にやらないと改善する時間がありませんね。レポート提出を求める授業はたくさんありますか。
柴田副学長:自分で調べてレポートを書くようなことはあまりありませんでした。
原:韓国の大学ではどうですか。
杉岡総長:韓国では,先生と学生の間がとても近くてよく話します。教官と学生という上下は踏まえつつも,友達とはいきませんが,親しく話すことができます。
柴田副学長:私もできるだけキャンパス内を歩いたり,ファカルティクラブまで昼食に出かけたりしますが,出会う学生さんが挨拶してくれないので寂しく感じます。アメリカでは,教官と学生の距離がもっと近いと思いました。
先生の方にもまだまだ戸惑いがあるのかもしれませんが,できるだけ先生方に近づいてアドバイスを受け,また九大の制度や先生も含めた資源を積極的に活用して,充実した学生生活を送っていただきたいと思っています。私たちも皆さん方の意見を参考にして,のびのびと学生生活を送っていただける環境を作っていきます。今日はどうもありがとうございました。皆さんの今後のご活躍を期待しています。

C&C(チャレンジ・アンド・クリエイション・プロジェクト)は,自分で考える面白さと創造性発揮の喜びを実感できるような機会を提供することを目的に,九州大学の全学事業として1998年に設けられました。
学生・大学院生自らがユニークな研究・調査プロジェクトを企画し,自由研究,起業研究,課題研究などのカテゴリーでそれぞれ数件が採択され,50万円が助成されます。また報告会が開かれ,特に優れた成果が得られたものには総長賞が贈られます。
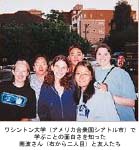
1994年10月,九州大学は国立大学としては初めて短期留学制度Japan in Today's World Program (略称JTW)を発足させました。これは,協定校の学部学生を対象に1年間日本の各分野に関する講義を英語で行うもので,2000年度の第7期生までに,欧米,アジアなどから157名を受け入れました。
また,1996年からは,JTWと並行して協定校へ1年間の授業料免除,単位互換を原則とする学生派遣を始めました。2000年度生を含めて45名の九大生が,欧米,韓国の大学に留学しました。

1998年11月に韓国の金鍾泌国務総理は,九州大学で韓日関係の発展を呼びかける講演を日本語で行いました。これを契機として,韓国政府は,九州大学を「韓国研究の拠点」と位置づけた5年間で約1億円にのぼる助成を行うことを決めました。
この助成金による事業の一環として,ソウル市の梨花女子大学校が夏期約1カ月間開講する「韓国語短期課程」に,毎年約15名の男女学生が旅費や授業料の支給を受けて参加しています。