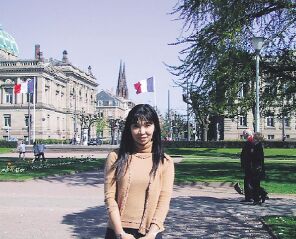~外国人短期留学コース(JTW)生のフィールドスタディ~ |
11月14日(水)、総合理工学研究院の森永健次研究院長の紹介により、フィールドスタディの一つとして、今年10月に来日したJTW第Ⅷ期生が、佐賀県西松浦郡有田町にある柿右衛門窯を訪ねた。そして、さらに、今年、重要無形文化材保持者(人間国宝)に認定された色絵磁器の14代酒井田柿右衛門さん(66)から、幸運にもお話を聞く機会を持つことができた。 「酒井田柿右衛門」といえば、唐津の中里太郎右衛門、有田の今泉今右衛門と並んで、「肥前の三右衛門」とよばれ、「柿右衛門様式」として、江戸時代から受け継いだ乳白色の磁器の釉(うわぐすり)の上に、赤や緑、黄色などの上絵の具(うわえのぐ)で絵付けを施した「赤絵」の技法が世界的にも有名。江戸時代に輸出された柿右衛門の磁器が、マイセンなどヨーロッパ各地の色絵磁器の発展に大きな影響を与えたことは、人々によく知られている。 JTW生は、14代から直々に窯元を案内してもらい、磁器の歴史や技法などについて、説明を受けた。JTW生の中には、これまで窯元を観たことがない学生が多く、同伴したチューターに日本語で書かれた説明についてしきりに質問するなど、大いに興味を持った様子で、観るだけでなく実際に作ってみたいという声もあった。 「”きれいなもの”ではなく、”美しいもの”をつくりたい」 |
 柿右衛門さんの窯元では、江戸時代から伝えられた材料を使って作品を作っていうるという。 「最近では、化学的に完全に処理された材料が多い。使いやすく純粋な材料を用いることで見た目に”きれいなもの”が多くできるようになったが、味気のないものとなっている。ここでは、昔ながらの技法で、不純物を取り混ぜた”美しさ”を追求したい」と現在の日本工芸の悩みも打ち明けながら、日本人が忘れかけている”美しさ”へのこだわりをみせた。 最後に、「若い世代にも広く、有田焼を通して日本伝統工芸への理解と関心を抱いてもらいたい」と述べ、柿右衛門窯元でのフィールドスタディを締めくくった。 |
 野田 寿美子(のだ すみこ) 法学府 国際関係法学専攻 博士後期過程 University Robert Schuman, Strasbourg III
前略 11月に入り、急に寒くなり、こたつを出した・・・というような話も耳にしておりますが、以下がお過ごしでしょうか。 フランス、ストラスブールに来て、早7ヶ月の月日が経ちました。通りは、黄色い落ち葉で埋め尽くされ、秋の趣に浸っていたところ、ここ数日、急に冷え込み、「ああ、とうとう冬がやってきた・・・」と感じています。 ヨーロッパでは10月最後の週末に、それまでの夏時間(日本との時差7時間)から冬時間(日本との時差8時間)へ移行しました。夏の間夜9時30分過ぎまで日が暮れなかったのに比べて、最近は、夕方5時30分にもなると、もう真っ暗になってしまうという、日の長さの大きなギャップに、最近は不便さえ感じてしまいます。 こちらでは、10月から新学期が開始するということで、私自身も、それまでの専ら語学習得に没頭する毎日から、ようやく今後の研究テーマに向けての勉強をスタートしました。その関連の話をちょっとだけ進めると・・・ 最近、フランスの新聞・ニュースで取り扱われているように、今月、中東カタールのドーハにおいて、開催されるWTO第4回閣僚会議は、今後のWTO体制にとって大変重要視されています。中国・台湾のWTO加盟も今回正式に承認されることになっており、今後WTOの貿易ルール、世界自由貿易の枠組み、それらに向けた新たなラウンド(交渉)の立ち上げの必要性は、ますます高まってきています。前回のシアトルにおける失敗、その原因とされる”WTO・自由貿易反対”の動きも、無視することはできませんが、貿易ルール・自由貿易の枠組み自体を破壊する動きは、断固として阻止されなければならないと感じています。 何だか、小難しい話に鳴ってしまいましたが、おいしいフランス料理を長時間(最低2時間!)かけて味わいながら、このような小難しい話題について議論するという、フランス独特の情緒に浸るのも、この留学の楽しみの一つかなあとしみじみと感じている今日この頃です。 では、皆様も風邪などひかれませんよう。 草々 ※野田さんは、九州大学から推薦されてフランスのルノー財団の奨学金を受け、昨年4月から今年の9月まで、フランスのロベルト・シューマン(ストラスブール)大学に留学しています。 |
前のページ ページTOPへ 次のページ
インデックスへ
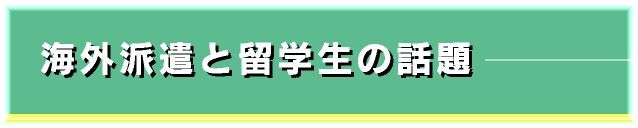 No.1
No.1