 | 法人化に伴って変更される重要事項 |
組織・運営、教育・研究、労務・財務等で、法人化に伴って変更される重要事項を簡潔に解説します。
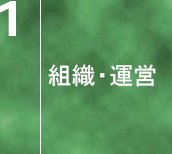 |
国の行政組織の一部であった国立大学は大学毎に法人格を付与され、九州大学は、国立大学法人九州大学が設置する大学となりました。これにより、国による予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定できるようになりました。教授会の合議中心だった運営をトップダウン型に切り替え、大学全体の意思決定の速度を上げるとともに、総長の統率力を大学運営・経営により効率的に反映させることができます。大学運営を着実に進めるために、役員会、経営協議会、教育研究評議会を置き、総長の意思決定を助けます。 九州大学では、役員に1名の学外者を登用し、経営協議会には13名の学外者が参画します。法人化に伴う組織・運営に関する重要な変更点を表4に示します。 |
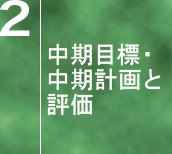 |
中期目標は、各大学の理念や長期的な目標を実現するため、あらかじめ各大学から提出された意見を踏まえ、6年間に達成するべき業務運営に関する目標として文部科学大臣が定め、各国立大学法人に示すものです。また、中期計画は、中期目標を達成するための具体的な計画であると同時に運営費交付金について予算要求する際の基礎となるもので、各大学が作成し、文部科学大臣の認可を受けるものです。 中期目標の達成度は、教育研究については、大学評価・学位授与機構の評価結果を尊重して、国立大学法人評価委員会が国立大学法人の運営全体を総合的に評価します。評価結果は、次期中期目標・中期計画の内容に反映されるとともに、運営費交付金の算定にも反映されることになります。 |
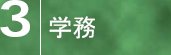 |
授業料等学生納付金(授業料、入学料、入学検定料)の額については、今まで国で定めていましたが、法人化後は国から示されている標準額を踏まえて、+10%の範囲内で大学で決定できるようになりました。(下限は定められていません。) |
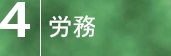 |
労働条件については、適用法体系が国家公務員にかかる人事院規則体系から、労働基準法体系に変わり就業規則を大学で定めることとなります。兼業制度を緩和し、専門業務型裁量労働制を労使協定に基づき導入します。 |
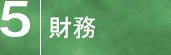 |
運営費交付金は使途を特定せず、各大学の判断で弾力的に執行することが可能となり、人件費と物件費の区分がなくなります。今後、運営費交付金には、効率化係数及び経営改善係数(病院収入のみ対象)が適用されますので、大学経営や外部資金の獲得に一層の努力が必要となります。 |
| 法人化前 | 法人化後 | |
| 設置者 | 国 | 国立大学法人 九州大学 |
| 運営組織 | 総長 副学長(4) 部局長等 | 総長 監事(2) 理事(8) (以上役員) 部局長等 |
| 意思決定 | 評議会(重要事項を審議) | 役員会(重要事項を議決) 教育研究評議会(教育研究面を審議) 経営協議会(経営面を審議) |
| 総長の選考 | 評議会の議に基づき総長の定める基準により、評議会が行う | 総長選考会議による選考 |