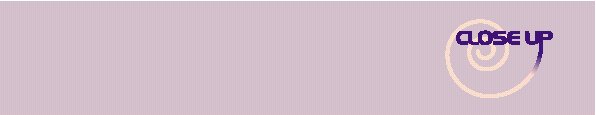
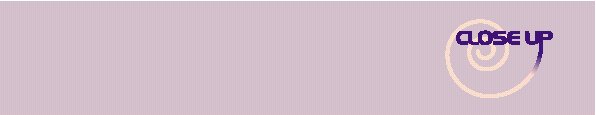
|
●タイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール 法学研究院長 吾郷 眞一 第二回アジア学長会議が終わって間もない十一 月末、ネットワーク・ポイント設置の具体化のた めの行脚が始まった。 第一弾はマレーシアのマラヤ大学である。マレ ーシアを代表する伝統ある大学で、九州大学とは 今までは関係がさほど深くはなかったが、第二回 九州大学アジア学長会議にアヌアール・ゼイン学 長とスワブ国際交流部長が出席され、緊密化がこ れから図られようとしているところである。国際 交流部をネットワーク・ポイントとし、法学部長 を中心とした連絡体制整備が合意された。 次に訪れたのがタイのタマサート大学とチュラ ロンコン大学である。これまたタイを代表する二 大学で、両者とも優劣がつけがたい権威を誇って いる。ナリ・タマサート大学長は、一九九九年の 大学サミット・イン・九州に始まり、二度のアジ ア学長会議いずれにも参加、最後は基調講演もお 願いした人で、ネットワーク・ポイント設置に関 しては初めから賛同を得ている大学である。タマ サート大学国際交流部をネットワーク・ポイント と指定され、現場に案内された。担当教官(団) については、これからつめることになった。チュ ラロンコン大学はすでに全学の交流協定が締結さ れており、ネットワーク・ポイントについても具 体的にどのようにするかということが話の中心となった。関係者四人ほどと昼食会を催していただ き、早急に担当支援教官を選任したいという学長 自身による約束を取り付けることができた。 一月末、インドネシア大学では、十月の第二回 学長会議に出席されたボディサントソ学長と、ソ ジョハルジョ国際交流センター長と面会した。学 長は、ネットワーク・ポイントについての説明を 私から聞く前に、学長会議の席上すでに同意する ことを明言していたことを強調され、ネットワー ク・ポイントを国際交流センターに設置するとと もに、担当教官としてソジョハルジョ教授を指名 すると述べられた。インドネシア大学は言うまで もなくインドネシアにおける最高権威であって、 キャンパスも町の中と郊外に大きいものを持って いる。この日はジャカルタ市に大きい被害を出し た豪雨の直後で、郊外のキャンパスから来る予定 だった工学系の教授はついに到着しなかったが、 ソジョハルジョ教授を中心に連絡を取り合ってい くことを確認した。 翌日、シンガポール大学では先方側から昨年九 月に九大と大学間協定を締結したことが想起され、 ネットワーク・ポイント構想に積極的に応じる考 えが示された。学長はオーストラリア出張中で欠 席だったが、国際交流委員長チョイ教授のほか日 本担当助教授二名、アジア太平洋担当課長、それ に私の希望で参加してもらったタン法学部長ほか 一名の法学部助教授が出席して効果的な会合が持 たれた。シンガポール大学側としては、KUARO に値するものとして国際交流課を指定し、二名の日 本担当助教授をNP担当教官とするという説明が あった。なお、ごく最近、このネットワーク・ポ イントの最初の利用例がシンガポール大学につい て発生し、興味深いので次に紹介する。 |
●シンガポール大学との一成果 KUARO 新開 章司 今年一月にNP設立に合意したばかりのシンガ ポール大(NUS )から、三月末に九大側のNP窓 口であるKUARO に学生受入れの要請があった。サ プライ・チェーンを研究する修士修了の学生が九 大での研究を強く希望しているとのことであった。 学生からの手紙や履歴書を参考に、細江経済学 研究院長に相談し、経済学研究院の古川助教授を 紹介いただいた。その学生は、古川助教授の指導 のもと五月からの短期留学が実現した。今回の例 は、NUS との学生交流協定を活用しての短期留学 となるが、経済学研究院、KUARO 、国際交流推進 室、そして留学生課が連携した学生の受入れが実 現したもの。各部署を有機的につなぐKUARO の機 動力が発揮されたケースであり、NPが効果的に 機能しはじめた一例と言えるのではないだろうか。 ●インド・ムンバイ大学およびインド工科大学マドラス校 総合理工学研究院 教授 村岡 克紀 インドはアジアの中でも学術上重要な位置を占 めるにもかかわらず、これまで九大との組織的な 交流がなされてこなかった。第二回アジア学長会 議実行委員会での検討の際この点が指摘され、総 合理工学研究院に在職するインド出身のバサ助教 授からの協力を得て、同会議にムンバイ(旧ボン  各学科主任教授へNPのプレゼンテーション(ムンバイ大学) |