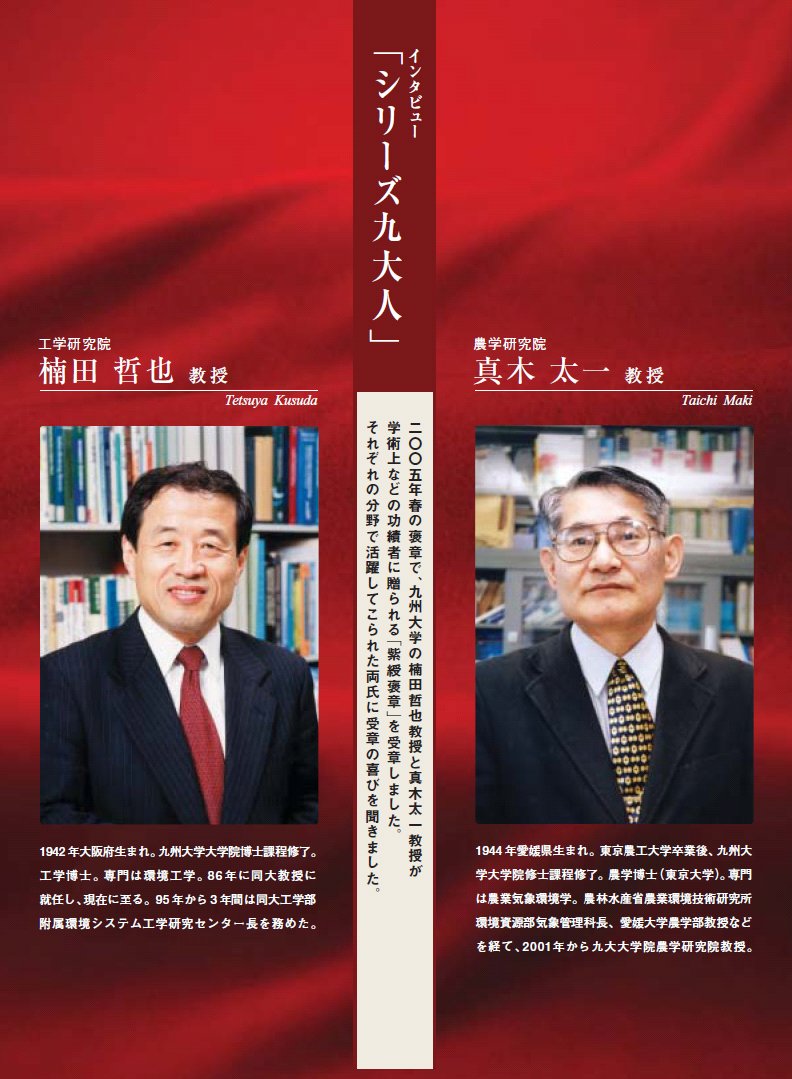
 | 風に関して約40年間みっちり研究して きました。おかげで「風の真木」と 呼ばれているくらいです。 |
| 農学研究院 真木 太一教授 |
―紫綬褒章の受章、おめでとうございます。先生のご専門は農業気象学ということですが。
真木 地球は現在、温暖化や砂漠化などの環境問題を背景に、気象条件の改善や環境制御調節が強く求められています。その中で私は、風が農作物に与える影響から防風・防砂林や防風垣といった風を抑える防風施設の研究まで、風に関して約四十年間みっちり研究してきました。おかげで「風の真木」と呼ばれているくらいなんです。
―農林省の農業技術研究所勤務時代には、南極地域観測隊員として氷点下四十度以下の世界を探検。現在は砂漠化防止技術の開発で摂氏五十度にも及ぶ灼熱(しゃくねつ)の砂漠で研究を進めていらっしゃいますね。
真木 私の研究のモットーは、科学の基本である自然環境の認識を深めると同時に、実際に活用するための技術化を積極的に進めることなんです。そして現地主義を貫くこと。中国のトルファン、タクラマカン砂漠などに一年以上滞在して、防風ネットなど防風施設の設置や緑化技術の気象的裏付け情報の提供、砂丘・黄砂の移動特性などの解明に取り組んできました。
―中国での研究内容を具体的に説明していただけますか。
真木 日中の気温が五十度に達する砂漠で防風林を作れば、熱風が抑えられることによって気温が下がり、緑化へとつながります。しかし、防風林を作るには何十年もかかってしまう。防風ネットならば、張るだけですぐに効果が発揮されるので手っ取り早いんです。
タクラマカン砂漠ではこれ以外にも「草方格」という防風施設を設置しました。草方格はアシワラやムギワラなどを一メートル四方の碁盤の目状に植えて作るんですが、砂が飛んでいくのを抑えることで、年間降水量がわずか五十ミリ程度というタクラマカン砂漠にもたちまち灌木が育ってきました。この草方格は鉄道や砂漠道路の保護用に試験的に導入されたものですが、このような取り組みがどんどん広がっていけばと期待しています。風害防止と砂漠の緑化は私のライフワークでもありますから。
―厳しい気象条件の中での研究ですが、困難に感じたことなどありましたか。
真木 これは南極でも砂漠でもいえることですが、持参した測定機器が現地でも正常に働くかどうかは常に不安ですね。スイッチを入れる瞬間は毎回緊張します。精密機械だから修理が簡単ではありませんし、現地で調達したり取りに戻れるものではありませんからね。
 ―そうして得られたデータは、気象改良のための基礎情報として非常に有用ですね。
―そうして得られたデータは、気象改良のための基礎情報として非常に有用ですね。
真木 私は基礎学問を体系化することを重要視しているんです。中国では、草方格がもたらす防砂効果を風速や気温、飛砂移動量の面から解明しました。このほかにも、山形県天童市のジャガラモガラ風穴の気流が季節によって逆転する特性や愛媛県西条市で吹く冷気流のメカニズムなどを解明して、農業や生活に有効利用できる気象資源としての可能性を示してきました。
―まさに基礎研究あればこそですね。では最後に、学生の皆さんにメッセージをお願いします。
真木 決して基礎学問を軽んじないことです。そして、得られる情報は貪欲(どんよく)に吸収して反すうし、必ず自分のものにすること。目標に向かって意欲的に動き、少しだけ出しゃばりながら、自分の手で未来を切り拓いてください。
 | 「寿命があるものは将来的にゴミになる」 という視点に立ち、モノの終着点を 見据えて現在の環境問題を見つめ直す。 |
| 工学研究院 楠田 哲也教授 |
―紫綬褒章、おめでとうございます。受章の実感はわいてきましたか。
楠田 まだ全然。知らせを受けて、自分が一番驚いたんですよ。
―今回、どのようなところを評価されたと思われますか。
楠田 環境問題を個々の問題ではなく、社会を含めてシステムとして解決を図るにはどうすればいいかという点にまで至ったことだと思います。
環境学と環境問題解決とは、ちょうど医学と医療に相当すると思うんです。学問として体系化されている医学に対し、医療はそれを提供する人と受ける人があり、そこに人間性や社会的な要素が数多く関わっています。環境学も同じで、生物や物理、さらには政治学や工学など幅広い要素で構成されている上に、その問題解決には、これら基礎学問に加えて人間の価値判断が大きく関わっているのです。
―具体的には、現在どのような研究に取り組んでいますか。
楠田 科学技術振興機構のプロジェクト「黄河流域の水利用・管理の高持続性化」などがあります。この研究の目的は、急速な発展を遂げ、水資源不足が深刻化している中国を舞台に持続性の高い新たな水循環システムを提案しようとするものです。ここでは、水不足の問題を一義的にとらえるのではなしに、流域の水循環や農業生産、土砂輸送、汚濁負荷と浄化に関わる機能などのシステムを観測・モデル化しようという観点から研究を進めています。
 ―楠田教授は学生時代、固体と液体が混ざり合った状態である「混相流」のメカニズムを研究されていましたよね。そういう研究から、システムという全体の研究に目を移されたきっかけは何だったのでしょうか。
―楠田教授は学生時代、固体と液体が混ざり合った状態である「混相流」のメカニズムを研究されていましたよね。そういう研究から、システムという全体の研究に目を移されたきっかけは何だったのでしょうか。
楠田 九州大学を卒業後、米国フロリダ大学の海岸海洋工学科で学んでいたとき、生態学の権威であるH・T・オダム博士の講義を受けて、環境事象をエネルギーの変化でとらえるという面白い発想を知ったのが最初でした。
帰国してからも、土木学会の関係で、大阪大学名誉教授である末石冨太郎氏から「環境を見る眼鏡」の訓練を受けました。「寿命があるものは将来的にゴミになる」という視点に立ち、モノの終着点を見据えて現在の環境問題を見つめ直す考え方です。例えば、窓から見えるビルを見て、「あれはいつゴミになるかなあ」とか「どこに持っていって捨てるんだろう」と、少し冷ややかな目で見るんです。そうするうちに、人間の行動を踏まえて環境問題を考えるようになりました。
―これからの環境問題を考える上で参考になる発想法ですね。
では最後に、学生の皆さんへのメッセージをお願いします。
楠田 環境学へのアプローチには幾つもの方向がありますから、まずは自らの人生の根幹となる学問を一つ身に付け、その後、その学問を基に対象領域を広げていくことをお勧めします。そうすると、論理の構築が方向性のはっきりした深みのあるものになり、筋道立った独特の考え方ができるからです。
また、環境問題は変化し続ける社会の下で生じていますので、解決し終えたということはなく、常に課題に満ちています。人類が健やかに存在し続けられるよう、共に手を携えて頑張りましょう。