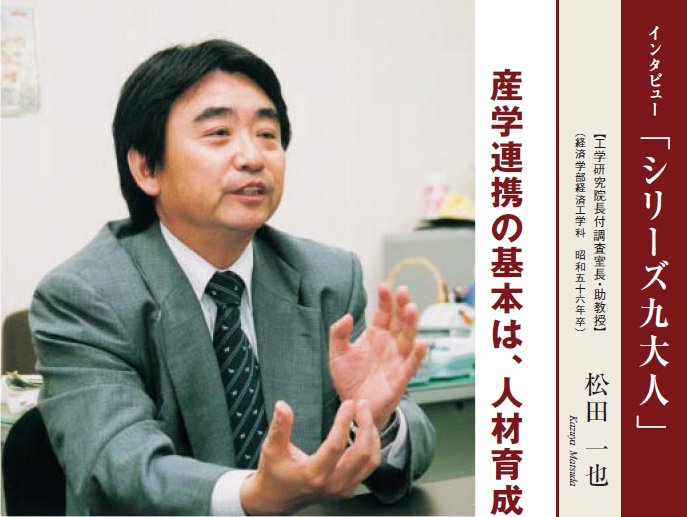
―工学研究院長付調査室長をまもなく離任され、九州経済産業局へ戻られると聞いて、伺いました。
まず、これまでの経歴を教えてください。
松田 経済学部の経済工学科の一期生として九州大学を卒業したのが、昭和五十六年三月。当時の福岡通産局に入って、環境ビジネス、産学連携などさまざまな仕事をしました。
特に、経産省が進める全国十九の産業クラスタの一つであるK-RIPという環境リサイクルの中核組織立ち上げに関わりました。他にも、産学連携による人材育成、技術開発のための補助金の交付、中国や韓国との国際的な経済交流など何でもやりました。
―工学研究院長付調査室長とは他の部局にないポジションですが、どういう仕事をされるのでしょうか。
松田 仕事は主に企業と大学をつなぐ、いわゆる産学連携がメインで、私で三代目です。代々、学外の産業人が務めていますが、これからは行政の感覚も必要ということで、村上敬宜前工学研究院長からご指命を受け、平成十五年三月に赴任しました。七月一日には、九州経済産業局に戻る予定で、既に四代目が後任として、同局から六月一日に赴任し、現在は、ダブル配置の状態です。
この二年間余りで、九州大学の約四百名の先生方との面識を得て、お顔、お名前、ご研究の内容などを頭の中に入れることができました。これまでの経験から二千社ほどの企業を存じ上げていますから、四百人の先生方と二千社のマッチングの可能性をさぐること、ただ合うか合わないかだけでなく、政策的な動向など加味して連携を創り出すというのが私の仕事です。九州大学知的財産本部とは常に連絡を取り合い、上手に連携して進めています。
 ―今、注目されている産学連携はどうあるべきだと思われますか。
―今、注目されている産学連携はどうあるべきだと思われますか。
松田 大学が他の組織と比べて輝いているのは、学生がいるからです。キャンパス内にこだまする若い人たちの声は、自分を励まし、新たなチャレンジへと導いてくれます。著名な先生の研究室を訪ねると、必ず学生諸君が元気ですね。先生と学生の間で知識とエネルギーの交換が相乗効果となって人材育成と研究が充実する。それが理想ではないでしょうか。
大学の使命はこれまで教育と研究にありました。今は、研究の中の教育との境界近くに、産学連携という範疇が生まれ、ウエイトを増しつつあると考えられます。中でも企業の中堅となる人材の育成、また、インターンシップなどで若い世代、つまり学生の人材育成など、総合的な人材育成が産学連携の基本だと思います。
 | 九大に居た間で一番うれしかったのは、 居酒屋で学生が声をかけてくれたことです。 後輩である学生から“先生の講義受けました。” と声をかけられ、じんときました。 |
―九州大学の産学連携はうまくいっているでしょうか。
松田 産学連携を支援する仕組みや体制は全国でもトップレベルにあると言えます。しかし、我々は黒子で主役は研究者の方々なわけですから、ポイントは、これからこの主役の研究者の方々のやる気と創造性を高める仕組みを如何につくるかだと考えています。私は、研究と教育と産学連携を分けることには反対で、三つを一体的にやれる人は相互作用で総合的なポテンシャルも高くなると思います。しかし、産学連携は相手のあることです。ピッタリ合えばいいが、なかなかそうはいかなくて、その際必要なのはマインドのベクトルの方向性が近いこと、研究とマインドのストライクゾーンが広いことです。私の感じでは、いい学生を育てられる人にはストライクゾーンが広い人が多い。仮に、研究分野が企業の要求に一番近い人よりも、二番目でも、そういうマインド、柔軟性を持つ人を企業に紹介することがしばしばあります。そういう場合の方が先々、その連携が発展する場合が多いからです。
 ―最後に九大や九大生たちにメッセージを。
―最後に九大や九大生たちにメッセージを。
松田 充実した二年四ヶ月でした。多くのすばらしい先生や学生諸君と知り会うことができて楽しかったです。九大はポテンシャルはとても高い。でもそれを生かし切れていない。もはや全てを真水のようにピュアでやれる時代ではありません。積極的に自分をアピールして、前向きに野心的にやっていけば、きっと世界に存在を知られる大学になると思います。この秋開校する伊都キャンパスは、そのために大きな財産になると思います。
九大生諸君も他大学の学生に決してひけをとりません。ポテンシャルがあり、素直で自分たちの頃よりレベルははるかに上でしょう。でも、やはりちょっと正直すぎるかなと思います。もっと野心的になってもいい。九大に居た間で一番うれしかったのは、居酒屋で学生が声をかけてくれたことです。後輩である学生から” 先生の講義受けました。“と声をかけられ、じんときました。
| このインタビューは、平成十七年六月三日に行いました。 |