江崎玲於奈先生、野依良治先生
二人のノーベル賞科学者が
若者へ語りかける
平成十八年十一月十五日(水)、江崎玲於奈氏(七三年物理学賞)、野依良治氏(〇一年化学賞)の二人のノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「二十一世紀の創造」(主催:読売新聞社、NHK、九州大学)が、「創造的若者へ!科学者からのメッセージ」をテーマに開催されました。
読売新聞西部本社の小島社長と、九州大学の梶山総長の挨拶に続き、野依氏が「人類の存続における知の融合」と題して、江崎氏が「自分の限界に挑戦しよう」と題してそれぞれ講演。続いて、伊藤早苗応用力学研究所教授をコーディネーターにパネルディスカッションと、客席との質疑応答が行われました。
会場の医学部百年講堂大ホールを埋めた、高校生約百五十名、九大生約七十名を含む聴衆は、二人のノーベル賞受賞科学者の熱いメッセージに聞き入っていました。
【江崎、野依両先生語録】
| 講演 |
| 野依良治氏 「人類の存続における知の融合」から |
| ● | たとえ小さいことでも、ゼロから自分で考える態度が大事だ。インターネット頼りの現代人は、自己家畜化が進んでいる。 |
| ● | 二十一世紀は、「文化」を尊ぶ「文明」を創るべきだ。科学者は、「知の融合」によって、芸術家や人文学者と共通の認識基盤を持ち、共通の理性で語りあえるようでありたい。「情報」が「知識」となり、「知識」が社会を豊かにする「知恵」となるためには、「知の融合」によってもたらされる科学者の文化的価値観や創造力が不可欠だ。未来の命運を握るのは人間自身の変革であり、未来技術の文化的統治が必要になる。 |
| ● | 自然科学に権力は無用。反権威、前衛・異端、若い皆さんにはそういう意気込みを持ってほしい。 |
| 江崎玲於奈氏 「自分の限界に挑戦しよう」から |
| ● | 人の能力は、天性と育成によって形作られる。自分が主役のシナリオ創作が人生だ。 |
| ● | 専門家は常に正しい訳ではない。 |
| ● | 失敗を恐れるな。失敗は、創造力を働かせてこれを生かして立ち直るチャンスだ。 |
| ● | 「しがらみにとらわれると、大事なことを感知できない」「大先生にのめりこむと、若い力を失う」「いろいろな情報から役に立つ情報のみ選ぶ」「自分を守るために戦う」「若々しい感性と好奇心を持て」がノーベル賞を取るための必要条件。ただし十分条件ではない。 |
 |
 |
 |
 |
| パネル・ディスカッション |
Q:先生方の豊かな創造性の秘訣は?(伊藤早苗教授:コーディネーター)
江崎:創造性は自ら抽出してつかみ取るもの。弥生は縄文の延長線上にあるのではなく、真空管の延長線上にトランジスタがあるのではない。未来は創られるものだ。
野依:日本人は問題を作るのが下手なのではないか。好奇心や「なぜだろう」と思う気持ちが大事で、マイノリティであることを恐れてはいけない。絶対やり遂げるのだという意志がまず必要。パスツールへの挑戦が私のテーマだった。
Q:何十年と研究を続けていける強い意志の源は?(小野寺玲子:九州大学二十一世紀プログラム四年)
野依:研究のおもしろさは、新しいことを生み出していくことのおもしろさ。暗礁に乗り上げることは、新しい問題を見つけることだから、進めなくともめげたりはしなかった。
江崎:悪戦苦闘を繰り返すわけだが、能力による必然と偶然の女神の共同作業である発見のよろこびが活力になる。量子力学では、物事の本質的なことを研究しているという自信とよろこびがあった。
Q:これからの科学者に求められることは?(山本耕太郎:明善高等学校二年)
野依:これからの科学は、社会と大きなつながりを持つようになる。これまでの科学は証拠主義で、過去と現在が相手だったが、これからは予測のサイエンス。将来が対象となる。
江崎:先端、インフラ、人間、人類の生存のための科学と科学には四分野がある。何をやるかはそれぞれで考えよ。
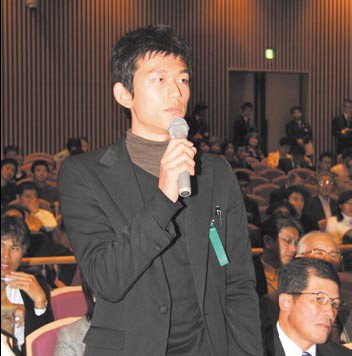 |
Q:留学したいが、海外生活で困ったことは?(金光優:筑紫丘高等学校二年)
野依:海外に出ると英語で困るが、友人たちが助けてくれるし、文化に触発される。
江崎:新しい所に行きなさい。英語を学んでおきなさい。世界には様々な考え方があると分かるが、サイエンスは共通だ。
Q:研究の方向性がぶれないようにするには?(赤川史帆:九州大学理学部四年)
江崎:思うとおりに研究が進んだとしても、結果はたいしたことはない。予期しないものに出会うことが大事。ただし、その価値を判断する力、鑑識眼は必要。それがないと、周辺的なものにばかり捕らわれて無駄が多くなる。人生も同じ。チャンスがあればそれをつかむことも研究のおもしろさだ。
野依:目的を設定して始めるが、やっている間に面白いことが見つかればそっちへ行ってもいい。我々が当初持っている知識はわずかなものだ。いい課題を見つけることが一番大事で、何かひらめいて課題が生じたら、それは君独自の研究になる。産学連携などでは管理された研究が必要だが、学術研究は知の創造なのだ。科学者は不確実性に賭けているのだが、それが心のよりどころでもある。
Q:理科離れについて(伊藤早苗教授:コーディネーター)
江崎:米国では、科学の時間は教えるより実験させて、発見するよろこびを体験させる。
野依:大の大人の優秀な科学者が寝食を忘れ没入して研究し創造に向かうわけだ。それくらいおもしろいのがサイエンス。それがどういうことか考えてほしい。
 |