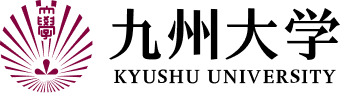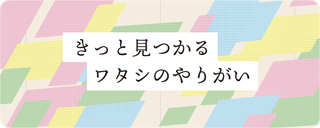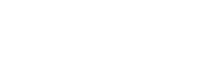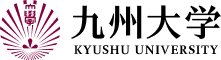About 九州大学について
Ⅱ九州大学の改革の主な内容
- トップページ
- 九州大学について
- 将来計画・大学評価・IR
- 大学改革等への取組
- 改革の大綱案
- Ⅱ九州大学の改革の主な内容
大学改革等への取り組み
改革の大綱案
II.九州大学の改革の主な内容
21世紀のわが国社会の潮流を背景とした大学への要請と現在の九州大学の抱える課題の二つのベクトルから、九州大学の改革の基本方向が浮かび上がってくる。
それは、一言で表現すれば、「時代の変化に応じて自律的に変革し、活力を維持し続けるシステムが内部にビルド・インされ、かつ国際的にも社会的にも開かれた研究大学の構築」ということになる。これが、九州大学の改革のコンセプトである。
こうしたシステムの構築を通して、全学一括して大学院重点化をはかり、かつ附置研究所の全国共同利用化あるいは中核拠点化を推進し、研究・教育水準の飛躍的向上をはかることによって、センター・オブ・エクセレンスとしての「大学院重点化大学」を構築することが改革の最終目標となる。
改革の具体的内容については、以下の8点に集約される。
-
博士・修士・学士課程教育の系統性
─学士・修士一貫と博士一貫の併存 -
教育組織と研究組織の分離と管理運営システム
─研究科・系教育と研究院の分離と連携 -
C O E 構築のための柔軟な協力システム
─教育研究プログラムと研究拠点形成プロジェクト -
柔軟で開かれた系の教育システム
─系・コ─ス制の導入と自由学際系及びハウス -
研究科と系の再編
-
附置研究所・附属研究施設等の改革
-
社会との連携の強化
-
国際的連携の強化
このうち、6の3つの附置研究所、健康科学センター、言語文化部、医療技術短期大学部の再編、及び7と8については、大学改革専門委員会の「続・九州大学の改革の大綱案」の報告をまって、引き続き検討し,結論を得たい。本章では1、2、3、4の改革の根幹部分にふれてみよう。なお、5については次章で論述する。
学士・修士・博士課程教育の系統性-学士・修士一貫と博士一貫の併存
21世紀の前半を見通すとき、九州大学での学士・修士・博士教育の系統性をいかなる形で確保するかは重要な改革のテーマである。
高度知識・情報社会が到来し、管理・専門・技術等高度専門職業人の社会的需要が増大することを考えれば、従来の4年制の学士課程の教育ではこうした新しい人材需要に十分に応える教育をすることができない。したがって、学士課程教育にさらにより高度な修士課程教育を付加した学士・修士一貫教育をするのが適当である。付加された修士課程は主として高度専門知識を身につけた職業人の養成のためのものである。当然、すでに学士課程を卒業し、社会で活躍している人々の再教育の場としても有効な役割を果たすものである。
九州大学では、学部学生定員を分母にし、大学院修士1年生を分子とした「大学院進学率」をみると、理系3学部→理系5研究科で70.8%と薬学部→薬学研究科で80.0%と高い「進学率」を誇っている(平成6年度)。もちろん、修士課程には他大学の卒業生がかなり入学しているので、「進学率」はこれよりいくらか低くなる。しかし、理系においては事実上過半の学生が学士・修士を通した教育を受けている。しかし、文系4学部→文系5研究科でみると24.9%にとどまっている。時代の流れが文系においても高度専門知識をもった人材の養成を不可避としているものの、過半の学生が修士課程に進学するようになるにはかなりの時間を必要とするであろう。
こうした時代の流れをふまえれば、九州大学が、21世紀初頭の社会経済情勢を先取りし、高度専門職業人の養成に教育の重点を移行して、学士・修士課程を一貫した系統カリキュラムで教育するという学士・修士一貫制を採用することが望ましい。
他方で、学士・修士一貫教育に踏み切ることに大きな問題点が存在している。わが国の大学は学士4年制をとっており、そのもとで大学入試の受験競争が行われている。九州大学だけが学士・修士一貫制をとるならば、分野によっては受験生から敬遠される可能性は否定できない。たとえ敬遠されなくても、4年で卒業して社会人となるコースが一般的であれば、一貫制に入ってきても4年で社会にでることを希望する学生はかなりの比率になるものと思われる。入学試験、4年卒業・就職、各種国家試験等大学教育をめぐる環境のなかで、他大学とのバランスを欠いて、九州大学だけが突出することのリスクは小さくない。21世紀初頭を見通して早くから学士・修士一貫教育に踏み切ったとしても、実体としての4年制の併用、4年制定員の漸減措置等激変緩和を伴う経過措置を慎重に進めていくことが不可欠である。
また、学士・修士一貫制を採用した場合、修士と博士課程の系統性をどう確保するかという別の問題が発生してくる。すでに、研究者養成の視点から博士前期、博士後期課程の一貫カリキュラムを採用している研究科も少なくない。さらに、飛び級制度を活用して英才教育をほどこし、期間を短縮して博士号を授与する動きも次第に活発となっている。国際的・先端的学術研究を担う人材の養成にとっては、先端的・専門的教育を系統的にすること、つまり修士と博士課程の系統性の強化は不可欠の課題である。
このように、修士課程は、高度専門職業人の養成のための高度専門教育としての性格と、優れた研究者の養成のための博士課程としての性格と2つの異なった位置づけが併存することになる。この場合、制度的には学士・修士一貫課程の組織(系)と博士(後期)課程の組織(研究科)に分け、前者の修士課程に博士前期課程的なコースを置くことになるか( βタイプ )、学士・修士一貫課程としての系と博士一貫課程(いわゆる博士前期課程と後期課程の定員を同じにし、一貫したカリキュラムで教育する。修士を取得せずに博士取得を原則とするが、修士取得も可能)又は修士・博士課程としての研究科の2つを併存する( γタイプ )か、二つの考え方があるが、今後の高度専門職業人の養成の急増と優れた若手研究者の養成という二つの異なったニーズを考えれば、学士・修士課程(系)と博士一貫課程(研究科)の併存を原則とするのが適当であろう。
ただし、学士・修士課程としての系と対応関係が弱い独立研究科については、研究科に修士課程を併設することが適当であり、また、文系にみられるように、4年制の学士課程で終了する学生が主流となっている間は、あえて学士・修士を一貫化せず、当面研究科内に修士を置く等の経過措置が必要と思われる。理系においても、学士・修士一貫に見合った法令の整備がなされるまでの経過措置は柔軟になされなければならない。いずれにしても、今後具体化に当たっては、多面的な影響に配慮しつつ、実行に移すことが適当であろう。
また、系の修士課程と研究科との間の学生の移動については、できるだけ柔軟に対応することが望ましい。
ここで、研究科は、学術研究の推進にCOE構築の中核的な役割を担うとともに、高度な研究能力をもつ研究者の養成に従来にも増して重要な役割を果たし、さらに高度の専門的知識・能力を持つ人材の養成や社会人の再教育においても大きく寄与することが期待される。系においては、従来の学士課程教育のうえに、より高度な修士課程教育を行うことにより、専門的知識・能力を持つ人材の養成や社会人の再教育、自己啓発のための学習機会の提供等、きたるべき高度知識社会にふさわしい役割を担うものと思われる。いずれにおいても、大学院教育の役割は今後ますます重要となるものと予想され、研究科や系における大学院に対する教育研究経費、量的整備、施設設備等の抜本的な充実が急がれる。
教育組織と研究組織の分離と管理運営システム-研究科・系教育と研究院の分離と連携
1. 教育組織と研究組織の分離と柔軟な連携-教育組織としての研究科・系と研究組織としての研究院
従来のシステムでは、教育研究組織として学部・学科があり、教官は学科内部の(大)講座に所属していた。このシステムのまま大学院重点化が行われると、教育研究組織としての研究科・専攻があり、教官は専攻内部の(大)講座に属することになる。いずれの場合でも、教育研究組織は一体化しており、学生の教育組織のユニットと教官の研究組織のユニットが1対1の関係にある。
これは、教育に対する教官の責任体制が極めて明確なシステムである。しかし、他方で時代の変化に対応して教育組織としての学部・学科や研究科・専攻を再編するに際して、研究組織としての講座の再編をも不可欠のものとするので、研究組織の伝統性・安定性が損なわれる事態もたびたび生じた。また、研究組織の伝統性・安定性を強調することによって、時代のニーズにあった教育組織の再編が断念されたことも枚挙にいとまがない。さらに、新しい学問の登場のなかで研究組織の再編が不可避な状況が生まれても、それが教育組織の再編の必要を伴わなければ、研究組織の再編が実現できない。
本来、研究組織のユニットと大学院や学部の教育ユニットなるものは、密接に関係しているものの、常に一体化しうるものではない。教育組織は、社会の人材養成のニーズ、多様な研究者の養成というニーズに対応してユニットが編成されるべきものであり、研究組織は、伝統的・基礎的な研究分野の継続性をベースに、先端的分野を積極的に取り入れる形で編成されなければならない。教育組織の編成原理が優先して、あるべき研究組織の編成の障害となったり、逆に研究組織の編成原理によって教育組織編成の適性化を妨げることがあってはならない。
ここから、従来の発想を脱して、教育ユニットとしてのコース(又は、カリキュラム群)と研究者の所属するユニットとしての部門=大講座(群)とを組織的に分離し、それぞれの独自の論理に基づくシステムをつくることが適当であるという結論が導きだされる。しかし、研究と教育が密接不可分なこと、管理組織が適性規模であること、いたずらに複雑な組織運営におちいらないこと等を考慮すると研究組織と教育組織を全学レベルで機械的に分離することは適当ではない。
ここで二つの案が考えられる。一つは、現在進められている「大学院部局化」という従来の路線の延長として、研究科を基本的な教育研究組織とし、その内部で教育組織としての専攻コースと研究組織としての部門に分離することである(A方式)。もう一つは、研究科及び系を教育組織とし、これとは別に研究組織としての研究院を設けることである。
そのうえで、教育と研究、とくに研究的機能をあわせもつ研究科教育との密接性を考慮して、両者の組織をほぼ1対1の対応関係に置くものである(B方式)。ここで、両者の共通点と相違点についてふれてみよう。
A、B両方式とも、研究科教育における専攻コース、系教育における系列コースと専修コースといった教育組織の編成と部門としての研究組織の編成が厳密に1対1に対応しておらず、それぞれの必要にもとづいて独自に編成することができる。特定の部門に属する教官が単独のコースの指導教官となるだけでなく、十分な条件を備えていると認められる場合は、複数のコースの指導教官になれる(これを重担と呼ぶ)など、柔軟な教育システムを組むことができる。ここに教育組織と研究組織の分離の最大の効用を認めることができる。
しかし、A方式を採用した場合、教育研究の管理運営において2つの大きな問題が生じる。
一つは、研究科教授会の構成をどうするかという点である。研究科教育には、研究科内にある部門に所属する教官だけでなく、他の研究科内の部門に所属する教官も指導教官として参加できることになる(重担)。こうした指導教官が教授会の構成メンバーとなる場合、当該教官は所属する部門のある研究科教授会と重担の研究科教授会の複数の教授会に人事を含む管理に参画することになる。当該教官が多忙となるとともに、管理運営上複雑な事態を招きかねない。他方、こうした重担教官を教授会構成メンバーとしない場合、当該研究科の大学院生の入学や博士の授与など教育の根幹にかかわることに意思決定権をもたないことになる。教育組織と研究組織の分離、重担可能という柔軟性をもたせたがゆえに、管理運営上解きがたい矛盾に遭遇することになる。
もう一つは、従来学部の中にあった教官組織(研究組織)を研究科に移すことから生じる問題である。このことによって、確かに教官が大学院教育に重点を置くという意識をもち、大学院の充実に寄与するが、その反面学士課程教育を軽視する危険性をもたらす。既に「大学院部局化」を達成した幾つかの大学では、こうした傾向が指摘され、各方面からの疑念が出されている。とくに、学士課程教育に配慮した教官人事が行われにくいシステムとなっていることは、学士課程軽視批判をより説得力あるものにしている。
A方式のもつこうした弱点を克服し、なお、教育組織と研究組織の分離のもつ柔軟性を実現するには、B方式を採用することが望ましい。これによって、教官人事をはじめ研究にかかわる事項は、部門に所属する教官によって構成される研究院教授会が、博士の授与をはじめ研究科教育にかかわる事項については、研究科の指導教官によって構成される研究科教授会が、系教育にかかわる事項については、系教育の指導教官によって構成される系教授会がそれぞれ意思決定することになり、A方式のような管理運営上の複雑性を排除することができる。教育組織として研究科と系、研究組織として研究院、この三つの組織の鼎立方式によってこそ、教育組織と研究組織の分離の妙味が発揮されることになる。また、現在生じている研究所と研究科との関係も、研究組織としての研究院と研究所が同じ立場で、共同で研究科教育に携わるという形となる。
しかし、三つの組織を個々バラバラの原理にもとづいて編成したのでは、いたずらに管理運営が複雑になり、教官がただ会議に追われて多忙になるとともに、教育組織にきちんとした責任を負えないものとなってしまう。三つの組織は、かなりの程度対応していることが不可欠である。とくに、「大学院重点化大学」として研究組織と研究科教育とが密接に連携していくためには、研究院の括りと研究科の括りが原則として1対1に対応することが望ましい。こうした組織編成を前提に、研究院及び研究科、さらに修士課程を併設する系への教育研究経費、施設設備などへの重点整備を行うことによって、「大学院部局化」とは違った方式での「大学院重点化」を達成することができるであろう。
しかし、研究院方式(B方式)を採用したとしても、なおA方式で指摘した第2の問題点は自動的には解決されない。
B方式は、教官が研究科にも系にも所属せず、それとは相対的に独立した研究院に所属し、研究科教育、系教育に対等に関与することから、教官が研究科教育に傾斜し、系教育軽視になるという批判は避けられるであろう。しかし、研究院の括りが研究科の括りと一致し、研究院教授会と研究科教授会のメンバー構成が重担教官以外ほとんど同じという実体を考慮すれば、やはり系教育軽視の傾向が生まれる可能性は否定できない。こうした問題を未然に防ぐシステムが不可欠となる。それは、以下の点に配慮したものでなければならない。
第一は、系教授会の安定性の確保である。系教授会が系指導教官全員によって構成されるのが適当であるが、肝心の系担当指導教官が毎年異なったメンバーとなることは、系の学生の系統的教育はもちろん、教授会の安定性の確保からいっても望ましいものではない。個々の系の指導教官は、系教育が一巡する4年ないし6年間を最低継続することが必要である。また、系の指導教官の全体の構成も、ベテランと中堅・若手とが適当に融合されることが望ましく、若手教官に集中することは厳に避けなければならない。その点では、ローテーション制を採用することが不可欠である。
第二は、系のカリキュラム編成に必要な教官と研究院が系教育に派遣する教官との調整を随時行っていかなければならない。研究院の一方的なイニシアティブでなされれば、充実した系教育ができなくなり、系教育軽視となってしまう。研究院教授会を代表する研究院長と系教授会の意向を受けた系長とが調整の責任を負うとともに、全学の教育研究計画委員会での承認を受けるシステムが適当であろう。
第三は、研究院での教官人事に当たっては、担当することが予定されているコースやカリキュラムの教官の代表が参加する等、系教育の観点が反映されるよう人事選考委員会を組織するとともに、選考基準に教育能力査定等を含めるなど一段の工夫が必要である。また、研究院の点検評価に当たっては、研究業績だけでなく、系や研究科の教育成果をも十分に取り込むことが肝要である。その場合、研究科においてティーチィングアシスタント制度を積極的に取り入れ、単位化するなど研究者養成課程において、系教育の経験を積み重ねることが重要である。
2. 管理運営と教育研究評価システム
教育組織として研究科と系を置き、研究組織として研究院を置くという新しい教育研究システムのもとで、全学的な管理運営体制も改めて大幅に改革されなければならない。改革に当たっては、以下の4つが重要なポイントとなる。
第一は、わが国の殆どの大学が採用してきた教育研究に従事する教官が管理運営の担い手となるという従来のシステムを維持するとともに、教官が教育研究に集中しやすい効率的な運営を実現し、時代の変化に組織として素早く対応できるリーダーシップを確立することである。換言すれば「民主主義」と「効率性及びリーダーシップ」を両立させるシステムをつくることである。これは、管理運営の基礎単位でもある教授会レベルにおいても、また全学レベルにおいても実現されなければならない。
基礎単位レベルでは、研究院及び研究所に教授会を置き、教官人事等重要事項を審議決定するとともに、教育組織においても、学生の身分や教育にかかわることを考慮して、それぞれ研究科教授会と系教授会を設置する。このように「民主主義の原則」を維持する一方で、研究院には研究院長が責任者となる部門長会議、研究科や系には研究科長や系長が責任者となる教育運営委員会を置いて、日常的運営の核となるとともに、教授会の審議決定事項以外のことについて審議決定できるものとして、教授会運営の効率性と部局長のリーダーシップを実現しやすいようなシステムとする。また、教官が三つの教授会にかかわるという複雑性を緩和するため、研究院と研究科が1対1で対応している場合は、原則として研究科長を研究院長が兼ね、両教授会が同じ日に開催する等運用上の工夫が望まれる。 全学レベルでは、部局長及び各部局から選出された評議員によって構成される評議会が全学の最高意思決定機関であること、全学の管理運営を統括する総長を全学の教官による選挙によって選出すること等最も基本的な点は、従来の方式を維持する。そのうえで、学内の意見をまとめつつ、組織として素早く対応するといった総長のリーダーシップが十分に発揮できる体制をつくるため、副学長を置く。九州大学が継続的に抜本的な改革を進めていくことを考慮して、副学長は3名とする。また、日常的運営を円滑にするため、評議会の審議決定事項を除く事項について審議決定できる部局長会議を置く。部局長会議の責任者は総長が兼ね、副学長もメンバーとなる。
第二は、センター・オブ・エクセレンスをめざして教育研究の面で常に活力を維持し続ける大学とするために、教育研究活動の系統的・継続的かつ厳しい点検・評価を行うことが必要であり、それを具体的に実現するシステムをつくることである。
具体的には、各研究院及び研究所教授会、各研究科教授会、各系教授会のもとに、それぞれ点検・評価委員会を置き、それぞれの部門、専攻コース、専修コース、系列コースごとにその研究、教育内容を点検・評価する。教育の評価に当たっては学生の意見を反映するよう工夫する。これらの点検・評価委員会は、各教授会直属とし、各部門長会議や各教育運営委員会のもとには置かない。
さらに、全学的な点検・評価委員会を評議会のもとに設置し、全学の教育、研究、管理運営の点検・評価を行う。この委員会は、各研究院及び研究所、各研究科、各系の点検・評価についても点検・評価し、必要なときは該当する教育研究組織に対して改善を勧告することができる。
また、各研究院及び研究所、各研究科及び系の点検・評価、全学の点検・評価に当たっては、第三者からの率直な意見・評価の提出を求め、それを参考にするものとする。
第三は、教育研究プログラムや研究拠点形成プロジェクト等センター・オブ・エクセレンスをめざした積極的な試みを確実かつ効率的に実施するため、全学の教育研究の企画調整機能をつくることである。この機能は、「重担」にみられるように研究科教育の充実のための研究院間の多様な協力、系教育と研究院の間の教官配置の調整等、組織を越えた協力・調整をスムースにする点でも必要となる。
具体的には、副学長が責任者となる教育研究計画委員会を設置し、こうした企画調整業務にあたる。
第四に、新しい管理運営システムのもとでは、民主主義的な運営をベースとしながら、「効率性」が重視され、総長や部局長のリーダーシップが強まること、研究院と研究科の分離、研究院・研究科と系のくくりの隔たり等から組織間の調整の機会が増すこと、学生のニーズが教育や管理運営に反映される必要があること等を考慮して、教官、職員、学生等の大学運営にかかわる疑問や意見を積極的にくみあげる組織として評議会のもとに新たに「苦情処理委員会」を設ける。これは大学の円滑な運営にとって欠くことができないものである。
最後に、こうした4つのポイント以外に管理運営にかかわって次の点への配慮がとくに必要であることを付記しておきたい。
- 教官の流動性が大きくなることが教育研究の活性化の要因の一つであるとしばしば 指摘されている。教官人事選考の基準において、外国人を含む九州大学出身でない教官 の割合や女性教官の積極採用等について考慮する必要がある。
- 大学情報を学内外へ積極的に公開することは、社会から期待されているとともに教 育研究を活性化する要因ともなるものである。教育研究の成果はもちろん、教育研究の 点検・評価の結果や目標への達成度等を含む広範な情報が、個人のプライバシーに対す る十分な配慮のもとで公開されるべきであろう。情報公開の方法としては印刷物による もののほか、大学情報のデータベース化とその活用を促進する。
- 九州大学の抜本的改革にかかわって、事務組織の大幅な再編も不可欠となる。事務 組織の再編に当たっては、教育研究支援のあり方を含めて、関係組織を中心に今後検討を進めていくものとする。
COE構築のための柔軟な協力システム-教育研究プログラムと研究拠点形成プロジェクト
教育組織と研究組織を分離することにより、両者の多様な組合せのなかで教育と研究の柔軟な協力システムを構築することができる。しかし、九州大学をセンター・オブ・エクセレンスにふさわしい大学とするため、科学技術・学術文化の発展を見据えて、研究科と研究院との1対1の対応を越えて、教育ユニットとしての新しいコースを暫定的に設定したり、とくに優れた学際研究を部門を越えて推進するため新しい部門を暫定的に設ける等一層の工夫が必要となる。前者を教育研究プログラム、後者を研究拠点形成プロジェクトとして、大学として特段の配慮が望まれる。
まず、教育研究プログラム制度は、以下のように進めることが妥当と思われる。
世界や国内レベルでの科学技術・学術文化の発展のなかで次世代学際領域や総合的学際領域の新たな分野での大学院教育の要請が高まっており、学内の研究者もこれに応じてかなりの研究成果を蓄積しつつあるというケースを想定する。
そこで、部門(大講座群)はもちろん研究院の枠を越えた研究者が協力して、研究科に設置された既存の専攻コースとは別に新型プログラムという新しい教育カリキュラムを組んで、系統的な教育を試みる。これは、期間を限定したものとし、これに要する経費については学内予算をもってあてるものとする。(STAGE I)
定められた期間の経過後、学内の点検・評価委員会がその成果を評価し、これに基づいて、教育研究計画委員会が存続か撤廃かについて審議する。著しい効果が認められた場合には、比較的長い期間にわたって学内措置で暫定的な新しい専攻コースを設け、系統的な教育を行う。ここには、既存の研究科の定員を配分して、新しい専攻コース所属の大学院生を募集するとともに、学内予算を重点配分する。また、既存の部門の教官が既存の専攻コースで大学院生指導を継続しながら、新しい専攻コースの大学院生の指導ができるものとし(重担)、さらに客員講座や寄附講座を設置して他大学・研究機関に所属する研究者の積極的な協力を得る。
定められた期間の経過後、点検・評価委員会がその成果を評価し、これに基づいて、教育研究計画委員会が存続か撤廃かについて審議する。専攻コース選択大学院学生数、教育研究実績、博士号授与等の状況をベースに特別コースの成果からみて適当であると判断した場合は、概算要求をへて、大学院生の定員増を伴った新たな恒久的コースとして設置する。これに伴い、新部門の設置や既存部門での新たな大講座の設置等により、教官の増員をはかる。(STAGEIII)
いうまでもなく、STAGE IからIIIへのステップは、必ずそれぞれのSTAGE を経過することが不可欠ではなく、必要であればSTAGE IIないしIIIを直接実現することもできる。また、既存のコースのなかに教官が協力して、恒常・時限問わず共通カリキュラムを設定することは、すでに幾つかの研究科で実施されており、社会人の増加、留学生への配慮等を考えれば、今後一層積極的に推進されることが望まれる。(STAGE 0) もう一つの研究拠点形成プロジェクト制度は、卓越した研究拠点(センター・オブ・エクセレンス)を積極的に育成するため、研究院の部門、附置研究所の研究部門に属する教官がそれぞれの部門を越えて共同で国際的・先端的・学際的研究をすることを支援するものである。これは、大学院生の教育を随伴しない研究に特化したものである。
具体的には、国際的・先端的・学際的研究を企画する教官グループの申出に基づいて、教育研究計画委員会によって選定されたプロジェクトは、一定期間にわたり、研究費の重点配分・導入、客員講座や寄附講座等の設置による外部の研究者の優先的採用等研究環境の重点改善の支援を受けることができる。(STAGE I)
一定期間の経過ののち、点検・評価委員会の評価をへて、教育研究計画委員会の審議によって存続又は、廃止される。ただし、とくに優れた成果をあげ、かつ長期的に継続する必要が認められるものについては、概算要求を経て新たな部門や講座の設置を目指す。(STAGE II)
なお、日本学術振興会による特別研究員制度は、若手研究者の研究活動を支援する制度として大きな役割を果たしている。教育研究プログラムや研究拠点形成プロジェクトの推進において、優秀な若手研究者の協力が不可欠であることを考慮して、これらのプログラムやプロジェクトにかかわる博士取得後の若い優秀な研究者にかかる学内独自に運用できるフェローシップ制度を設けることは、COE構築にとってより強い追い風となるであろう。
柔軟で開かれた系の教育システム-系・コース制の導入と自由学際系及びハウス
本学は、学術文化の進展と高度知識社会の展開に対応し得る優れた資質を備えた人材を育成するために、大学院の修士並びに博士課程教育の充実・拡大をはかるとともに、学士課程の教育を見直し、広い視野と豊かな人間性をもち、専門分野等の領域において指導的な役割を果たし得る専門職、技術職及び研究職の養成をめざして、教養・専門教育を統合した学士・修士の一貫教育を創造する。そのために学部・学科制に代わる柔軟で開かれた教育システムとして系・コース制を導入するとともに、一層大きな柔軟性をもって全学協力して教育を実施する系として自由学際系を設け、専門分野が異なる学生の間の交友関係の育成と学生の学習意欲の向上を目的とした教育施設「ハウス」を設ける。このほか、新しい系教育を豊かに創造していくために、教育目標を実現するための一貫カリキュラムの創造、今後ますます重要となるマルチメディアと情報ネットワークの利用を含めた授業方法の改善及び教育の情報化、学生による授業評価を含めた効果的な教育の点検・評価法の導入等を積極的に推進する。
-
系・コース制の導入
これまでの学部・学科の制度は、学生が専門分野と自らの適性についての理解が十分でないままに入学時点において学部・学科を選択せざるを得ないこと、入学した後で学生が自ら所属する学部・学科への不適性を自覚したりそれとは異なる分野に強い学習意欲をもつようになっても進路変更が困難であること、さらに、学士課程学生に対して期待されるものとしては学習内容の幅が狭くなりがちであること等の問題点を抱えていた。これらの問題点の解消をめざして柔軟で開かれた教育システムとして系・コース制を導入する。
系は伝統的な学問体系とその相互関係、養成する人材の専門性、並びに学問の総合性の確保を考慮して、専門分野の幅をこれまでの学部よりも広いか又は、同程度にくくって設けられる。各系には、その教育目的を達成するために、専門系列ごとのコース(系列コース)及び専門分野ごとのコース(専修コース)を設ける。学士・修士課程の学生はいずれかの系に入学し、一定期間教育を受けた後、いずれかの系列コースに所属するか、主専攻・副専攻カリキュラムを選択する。修士課程においては、いずれかの専修コースに所属して教育と研究指導を受ける。ただし、全学生が卒業時点で国家試験の受験を求められるため、入学時点から専門的かつ系統的教育が不可欠となっている医学系の各コースについては、系一括入学ではなく、医学、歯科医学、薬学の各コースによる入学が適当である。
所属コースの決定に当たっては、学生の自主的・自立的な選択希望をできるかぎり尊重するとともに、修得科目内容、履修成績、並びに教官配置、施設・設備等を考慮する。所属コースの変更を希望する者に対して、可能なかぎり変更を認める。もちろん各コースには定員枠が設けられるので学生の間には一定の競争が生まれる。一定期間以上在学し、所定の単位を修得した者で、希望する者に対しては、学士の学位を授与する。
学生が学習過程で学際的知識を身につけたり、大学間の移動による多様な教育機会に接することによって、より総合的な人間として成長していくのを積極的に推進していくため、各系の学生定員に比較的広い枠を設けて、系の変更や他大学からの編入学を容易にする。とくに、他大学からの編入学を確保することは、本学の教育研究活動を活性化するうえで重要である。これにより、学生の自主的・自立的な専門分野の選択に一層柔軟に対応することが可能になる。
このように系・コースの制度は、学生の自主的・自立的な選択に柔軟に対応するとともに、教育組織の間の壁を低くした開かれた教育システムをめざすものである。 -
自由学際系
柔軟で開かれた教育システムとしての系・コース制の中で一層大きな柔軟性をもった教育システムとして自由学際系を設ける。自由学際系はそれ自身の教育システムが柔軟であることを特色とするとともに、本学の学士・修士一貫の教育全体に一層の柔軟性を付与する役割を果たす。自由学際系は本学の基幹総合大学としての総合力を発揮して全学の協力でもってその教育を実施する。自由学際系は、特定の範囲の専門分野の枠の中で固定化される総合科学部といった性格のものと異なって、全学のあらゆる教育研究資源を自由に使うことによって教育がなりたつものである。自由学際系はそれ自身が閉じた教育組織ではなく、本学の他の系の間にあって、系の壁を越える媒介の役割を果たしながら、それ自身で、既存の専門分野の枠から抜けでて未開拓の分野で独創的、創造的な能力を発揮できる人材の育成を目標とする。
学生の特質は多様であり、準備された固い枠組みのもとでの教育よりも、自らの選択によって学習を進めることが可能な教育システムによってその能力を十分に発揮することができるタイプの学生もいる。自由学際系は学生自らの力で統合化・総合化することを重視した教育を行う。自由学際系においては、独自の授業科目は少人数クラスによる課題学習及び定められた学際テーマのもとでの科目群だけとし、それ以外については学生は他の系の科目や全学共通教育科目を履修する。各系は施設設備における制約等を除いて、その授業科目を自由学際系の学生に開放する。一定期間の教育の後は主専攻と副専攻を定めて科目履修をし、修士課程においては自らの学際的研究課題を定めて、修士論文作成を目標にして必要な科目履修をする。
自由学際系は専門分野を定めないで入学でき、さらに複数の専門分野を学習できる教育システムとする。自由学際系の入学者選抜においては従来からのものと違った方法が採用される。そこでは固定された方法によらず、入学後の綿密な追跡調査を含んだ大胆な試みが実施される。また、入学後の学生についても他の系や他の大学へ転学することや、他の系や他の大学から自由学際系への転・編入学をできるだけ可能とする。
このように自由学際系はさまざまな課題を受け止めて設けられる従来見られないような新しい教育システムである。とくに学生の自主性・自発性に大胆に依拠した教育が進められる。したがって、当然のこととして、そのリスクを最小限に押さえるシステムも備えられなければならない。その核となるのは、学生指導の体制並びに少人数教育の重視である。また、安定した教育が継続できるための責任体制の構築が不可欠である。そのため履修指導と課題学習・学際テーマ科目の担当を主な任務として自由学際系を担当する教官を置く。 -
ハウス
本学は、個別的な専門性にとどまらない創造性と豊かな人間性を有する人材の育成をめざして、広い視野と確実な基礎能力を育てるとともに、感性・知性・理性のバランスのとれた教育を実施する。さらに新しい可能性が開かれつつあるメディア教育を積極的に取り入れるなど、柔軟で効果的かつ効率的な教育の創造をめざす。そのような効率的な教育が真に効果的な教育成果を生みだし得るためには、そこで失われがちな個性と個人交流を重視した教育を、それと並行して推進することが不可欠である。学生は、教育の場での教師との交流並びに学生相互の交流を通して、知恵を使って問題を処理する能力や集団の中で分担し指導する能力を培い、自らの豊かな人格形成を促進し、学習に対する自主性・能動性を身に付け得る。とくに、現代の学生は、受験教育体制のもとにあって人間的交流を通して社会性を身に付ける機会が少なかったうえに、お互いに切磋琢磨するほどの深い交流を避ける傾向があるので、教育を通しての交流の機会を積極的につくりだすことが必要である。交流によって生まれる広い交友関係は、学生の卒業後の活動の幅を広げるうえでの財産となることが期待できる。
本学はこれらの教育の課題に積極的に応えるために「ハウス」を設ける。ハウスは、学生に幅広い教育機会や交友関係を与えるために、学生と教官との密度の濃い接触をつくりだすために、また、学生の学習意欲を啓発しそれに応えるために、設けられる新しいタイプの教育施設である。ハウスは正課教育としての少人数教育を柱とし、それに日常的な学生の自主活動及び生活と学習を通した相互交流を結合させる。そのためにハウスには学習室及び生活個室を設ける。ハウスは、隔離されがちである外国人留学生と日本人学生を結び付け、相互理解をめざして日常的に交流する場としても機能する。ハウスは単なる福利厚生施設としての学生宿舎ではなく、また、単なる自主活動施設・交流施設ではなく、これらの性格を合わせ持った教育施設である。ハウスは夏休み期間中等大学訪問者の宿舎として用いる。
ハウスには希望する1年生、2年生及び外国人留学生のほか、大学院学生等の上級生がチューターとして加わる。ハウス参加学生の決定、ハウス指導教官の決定など、ハウス運営のための組織を設ける。
- トップページ
- 九州大学について
- 将来計画・大学評価・IR
- 大学改革等への取組
- 改革の大綱案
- Ⅱ九州大学の改革の主な内容