支援システムで医療現場や子育ての不安や負担を少しでも軽くする
Discover the Research Vol.8 システム情報科学研究院 助教 宮内 翔子(みやうち しょうこ)
研究者が自身の研究にかける情熱の源泉というのは純粋な興味だけでなく、実生活の不満からくることがよくあるそうです。システム情報科学研究院の宮内翔子先生もそのひとりで、自身の子育てで経験した不満、不安をもとに子育ての支援システムを開発されています。今回は、そんな宮内先生に主な研究内容と将来の展望についてお話を伺いました。
目指すものは一人一人に合わせた支援
まずは先生が研究されている研究内容を教えてください。
私の専門は支援システムの設計です。AIや画像処理、三次元形状モデルなどの技術を応用してパソコンやスマートフォンなどのデバイスで稼働する医療や子育ての支援システムを設計しています。とくに三次元形状モデルには昔から興味がありまして、例えば10人の脳があるとしましょう。顔と一緒で、一人一人脳の形はバラバラです。この個体差というのを数値的に記述する、ということをずっとしてきました。
支援システムもまたコンピュータ上のものですから、数値的に表現できないと設計できません。手術のシミュレーションをするとき、患者一人一人に合わせたモデルでナビゲーションできないと事故につながってしまいます。そうならないために実世界の三次元的なデータを組み込むことでより正確で、安全なシステムの設計を目指しています。
どのような機能の支援システムを設計されているのですか?

まず、パソコンでは主に医療向けの支援システムを設計しています。例えば、MRIの画像や血圧情報など患者のいろいろな生態情報をAIに読み込ませて疾患を分類させたり、手術現場でどのような手順で進めるのかをナビゲーションさせたりするようなシステムの設計に携わっています。ダヴィンチのような内視鏡手術支援ロボットを用いた手術でAIが「次はここに血管があると予測されるので避けましょう」みたいな支援ができるようになるのが目標です。
また、スマートフォンでは主に子育ての支援システムを設計しています。例えば、生まれたばかりの子どもは首がまだふにゃふにゃですから、とくに初めての子どもですと、抱っこは緊張しますよね。それは親だけでなく、子ども側も同じだと思います。そこで抱っこしている親だけでなく、抱っこされる子ども側も安心できる姿勢とはどのようなものか、スマートフォンで動画を撮りながら「今の姿勢は何点です」「もっといい姿勢にするにはこうしたらいいです」みたいにガイドしてくれるような支援システムを設計しています。
自身の体験から子育て支援の領域にも
なぜ先生は支援システムの設計に進まれたのですか。
手をなくした方が代わりにロボットの義手をつけて制御する、のような工学と生物のつながりに昔から興味がありました。そこから生体工学にたどり着きまして、工学の力で医学の分野を助けることに興味を持つようになり、学生のとき医療支援システムを開発されている先生の研究室に所属しました。その後、自分で子育てを経験してみて、「もっと子育てにも支援が必要なのではないか」、「せっかく技術があるのだから生かせればもっと子育てを楽にできるのでは」と思うようになり、子育て支援にも広げてきました。
はじめての子育ては不安だらけですものね。

誰もが大変で、でも試行錯誤しながら何とかできてしまっているのが子育てです。正直、支援システムがなくてもすごく困るものではないと思います。でも、あったらきっと便利なもののはずです。せっかく楽できる可能性があるのなら、少しでも負担を減らせるのなら、貢献したいという気持ちでやっています。おそらく子育ての方法はそれぞれのやり方で問題ないのですが、誰かに「問題ないよ」「それで合っているよ」と肯定してもらえるだけで安心できたり、不安がちょっと和らいだりすると思うのです。
あと、抱っこのほかに、私がやりたいもののひとつとしては授乳姿勢です。子どもによって、お母さんによって形や姿勢などいろいろなバリエーションがありますからより安定する、安心できるやり方をガイドできたらなと考えています。
イノベーションは異分野融合から生まれる
先生の研究の特徴や強みなども教えてください。

本学に限定したとしても、支援システムを開発されていたり、医療や福祉の分野を研究されていたりする先生は何人かいらっしゃいます。でも、「医療と支援システム」「子育てと支援システム」のように別の分野と支援システムを組み合わせて研究されている工学の先生というのは多くはないように思います。とくに、工学という分野に身を置きながら、子育てという自分自身で経験したことをもとに子育て支援、福祉の方向で研究しているというのは、私ならではなのかなと思います。
先生の研究には専門的な知見も必要に感じます。
それはおっしゃる通りで、私はあくまで工学の分野しかわかりません。そこで工学的な部分については私が担当して、それぞれの専門的な部分については医師や助産師の先生に共同研究というかたちでご協力いただいて進めています。
研究の一丁目一番地は現場を知ることから
これまでの研究で印象に残っているエピソードを教えてください。
先ほどお話しした通り、専門家と共同研究している関係で、現場を見学させていただく機会がまれにあります。例えば、実際のロボット手術の現場でどのように先生方が連携されているのか、というのを見ることができるのは普通ではできないでしょう。また、子育て支援でも、実際に口唇口蓋裂児(上唇や口蓋などが左右に分裂するような亀裂が生じた状態で生まれること)の哺乳手技を確立された先生と一緒に研究しています。その手技を実際に見せていただいたり、どのような想いで問題を解決してこられたのかを聞いたりできることも貴重な経験でした。
やはり現場の声を聞くというのは大切なのですか。
とても大切です。私たちが工学で目指している技術的な新規性と、専門の先生方が現場で求められているものが違うということはよくあることです。私たちがこれくらいの技術でいいのかと思うこともあれば、すごく技術的に実現が難しいことを依頼されることもあり、それもまた新しい課題として勉強になります。
学生から質問のしやすい先生でありたい
学生には何を意識して指導されていますか。
学生たちができるだけ質問しやすい雰囲気作りを心がけています。学生が質問したいときというのは、そこに興味を持ってくれているときだと思いますから、ストレスなくスッと質問できる環境にしてあげたいのです。私のゼミでは週に1回のペースで研究の進捗を共有する場を設けており、そこではどこまで進めたのか、何か問題はあったのかなどこちらから積極的に声をかけて密に話し合うようにしています。また、それ以外の場でもSlackというコミュニケーションアプリなどでメッセージが送れるようにし、学生から何かメッセージがあればその都度、丁寧に答えるようにしています。
誰の手にも支援システムが当たり前な世の中に
宮内先生の今後の展望を教えてください。
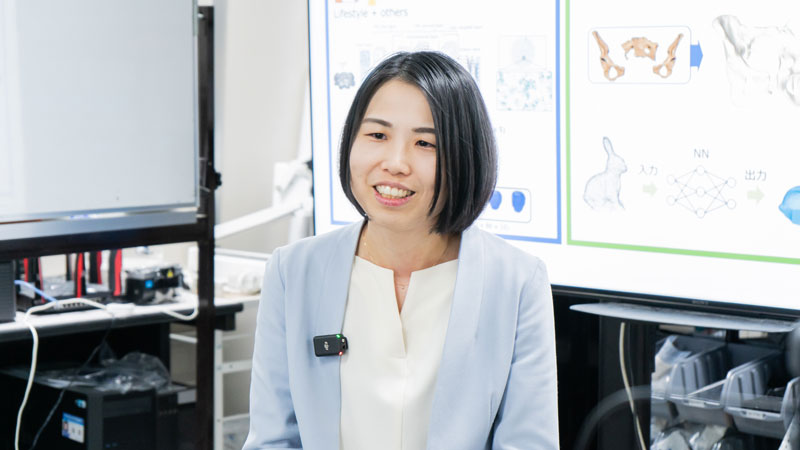
今は研究成果を研究室の中で閉じてしまっている部分が大きいので、設計している支援システムを世に出していきたいです。5年後くらいの短期的な目標としては子育ての支援システムを世に出せればなと。多くの方の手に届くようなシステムにするために、今や誰の手にもあるスマートフォン向けのアプリとして設計しています。それこそ産院を退院されるときに先生から「お守りとしてこのアプリを入れておいて」と言ってもらえるような、子育てのデジタル教科書のように使ってもらえるような世の中になったら嬉しいですね。
また、夢みたいな話かもしれないのですが、審査がとくに厳しいことで知られる医療分野でも、将来的には支援システムを世に出せたらなと思っています。
最後に、進路に悩む中高生に何かひと言いただけますか?
すでに何か目標がある方はそこに向かって進まれたらいいですし、目標がない方も今はそれでいいのだと思います。私もこれまで研究してきたなかで興味は移り変わってきてその都度、興味のある分野を深めてきました。とりあえず何となくでもいいので今、できること、してみたいことをやってみて、その過程で何か強く興味が持てるものを見つけたときにその道に突き進む、という方法もあるでしょう。一人一人が今できることをやっていけたら、それだけできっと今よりいい世の中につながっていくと思います。
宮内先生の研究の詳細については、研究者情報をご覧ください。









































