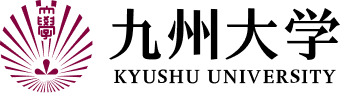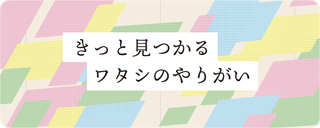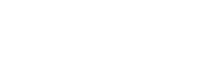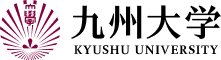-
カテゴリ別
-
場所
-
最新のお知らせ 年間スケジュール(就職対策講座等) OB・OG情報 システムの利用方法 学内合同企業説明会(「九州大学生のための業界・企業研究」) 学内企業研究セミナー / 個別企業説明会 公務員・教員等採用情報 就職相談 就職情報室 キャリア教育 低年次学年向け情報 インターンシップ等(学生向け) TOEIC対策プログラム 博士人材のための就職支援(学生向け) 外国人留学生のための就職支援 未内定の学生及び既卒者(卒業後3年以内)の皆様へ 障害のある学生のための就職支援 部局独自の就職支援 東京・大阪・博多駅オフィスの利用 各種情報サイト 過去の就職状況 採用選考に関する指針 学内合同企業説明会 博士人材のための企業説明会(企業向け) 本学へのご訪問 求人情報ご提供 OB・OG名簿ご提供 インターンシップ等(企業向け) 外国人留学生の採用 採用選考に関する指針 就職担当 よくあるご質問
Research Results 研究成果
オートファジーが膵癌を支える細胞の活性化に関与している事を発見 -全く新しい膵がん治療法の開発に期待-
2017.05.09研究成果Life & Health
九州大学大学院医学研究院の中村雅史教授、九州大学病院の仲田興平助教、大学院3年生の遠藤翔らの研究グループは、膵がん細胞の転移、浸潤に影響を与えている膵星細胞の活性化にオートファジーが関与している事を発見し、膵星細胞のオートファジーを抑制することが、新たな膵がん治療法となる可能性を見出しました。
膵がんは5年生存率が9.2%であり、他のがんと比較しても極めて予後が不良な疾患で、その予後の改善は社会的急務と言えます。がん組織の中には、がん細胞の他に線維芽細胞を中心とした“間質”と呼ばれる構造があり、この間質に存在する細胞が、がん細胞の転移、浸潤を促していると言われています(癌間質相互作用)。膵がんで癌間質相互作用の中心を担っている細胞が “膵星細胞”です。これまで本学の中村雅史教授、大内田研宙助教らは膵星細胞が膵がんの悪性化に重要であると考え、膵星細胞の活性化に関する研究を行ってきました。
“オートファジー”は細胞が自己成分を分解するシステムの一つですが、老化や免疫、さらには、発がん、糖尿病、神経疾患など様々な疾患に関与していることが報告され、現在、世界中で大きな注目を集めています。今回、研究グループは、膵星細胞のオートファジーを抑制する事で膵星細胞から分泌されるIL-6;Inerleukin-6やコラーゲンの産生が抑制され、その結果、膵がん細胞の転移や、浸潤が抑制される事を明らかにしました(図1右図)。また、膵がん細胞と膵星細胞を移植したマウスにオートファジー抑制剤であるクロロキン;CQを投与したところ、がん細胞の肝転移や腹膜播種が抑制される事も確認しました(図1左図)。
予後が不良な疾患と言われている膵がんですが、本研究結果は、膵星細胞および膵がん細胞のオートファジーを抑制することが膵がんに対する新たな治療法となる可能性を示唆しており、その結果、膵がんの予後が改善することが期待されます。
本研究成果は、米国科学雑誌「Gastroenterology」の2017年5月号に掲載されました。
研究者からひとこと
膵がんの予後は他のがんに比べてまだまだ満足できると状況とは言えません。本研究結果が膵がん治療のブレイクスルーとなる事を期待し、今後さらに研究を進めて参りたいと思います。
- 本研究についての詳細は こちら