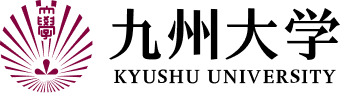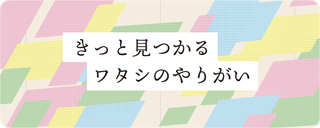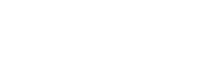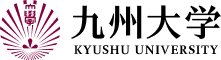超高齢社会に社会学からの解
日本は世界に例を見ない超高齢社会。既存の経済や政治の枠組みだけでは、パンデミックや戦争が迫るこの時代を乗り越えられませんが、ジブリ作品がこの難局を克服するヒントを与えてくれるかもしれません。
2023年2月、定年退職を間近に控えた九州大学の安立清史教授が福岡市の伊都キャンパスにて最終講義を行いました。安立教授は2000年から導入された日本の公的介護保険制度は、その大きな成功ゆえに「成功なのに失敗」と評価されていると言います。これは奇妙なパラドックスです。政治家や経済学の人達が口を揃えて言う、資金や労働力が不足する「悲観的」な未来の克服には、社会学的な新しい見方や枠組みが必要です。今回は、安立教授が社会学者としてのキャリアを通じて取り組んできたテーマについて語ります。
専門分野について教えてください。
福祉社会学が専門の社会学者です。社会学は、多くの人にとって学校で習う社会科と区別がつきにくいため難しいと思われがちです。でも自分たちの生きているこの「社会」を客観的に自己認識するための学問なのです。スポーツ等でいう「ホームとアウェイ」の考え方で説明してみましょう。サッカーのワールドカップ予選では、2つの国がお互いのホームグラウンドで試合を行います。自国での試合だけでは、そのチームの本当の強さが分からないからです。慣れた環境の外で戦う姿を見れば、チームの本当の力を計り知ることができます。
この「ホームゲーム」の視点から社会を観察するのが社会科です。社会科では、その国のあり様や、社会制度や法制度、価値観、歴史やそこに暮らす人々の特徴などを学ぶことができます。その目的は、自らの住む社会の成り立ちを理解し、社会の制度やルールにしたがう国民となることが期待されています。
それに対して、社会学では国を「アウェイ」の視点から観察します。その国の客観的な社会の構造、価値観、行動様式、暗黙の規範、意識、行動などを比較社会学的な観点から眺めると、この社会はもっと良くなるのではないかと疑問と問題意識を持つことになります。つまり第三者の視点からもこの社会を捉えるのが社会学です。
私の大学時代の先生だった見田宗介氏は、高校生の時に家族に馴染めず家出を考えていたそうです。大学教授になった後も、西洋から輸入された学問を鵜呑みにせず、メキシコ、ペルー、インド、東南アジアの人々から学ぶことで、異なる価値観を理解しようとしました。私もまた今の日本社会のあり方に違和感や疑問を抱く一人です。「超高齢社会」という考え方こそ、その一例です。
どのような経緯で福祉社会学を専門にしたのですか?
1994年に在外研究としてロサンゼルスでボランティアとNPOの研究をするために渡米しました。1980年代から日本全国で一人暮らしの高齢者を支援するボランティア活動が広がっており、私もその全国調査に参加していましたから、日本型の福祉ボランティア団体とアメリカのNPOの違いを比較社会学の視点から考えるようになりました。アメリカのNPOは、日本のボランティア団体と違い、パワフルで社会を変えていく力を持っていました。そこには目を見張るような違いがありました。アメリカには、かつては「全米退職者協会」として知られ、現在は「AARP」と呼ばれる、高齢者のための大きな全国組織があります。こうした団体を通じて、アメリカでは「定年制度」(これは英語では、年齢を理由とした強制退職制度と訳されます)が違憲であり、年齢差別であることが社会的に周知されていきました。アメリカでは、1960年代から1970年代にかけて、人種、性別、年齢による差別に抗議する三つの大きな社会運動が起こりました。これらの運動は社会を大きく変えました。
帰国後、日本の高齢者運動の関係者を対象に調査を開始しました。日本の「老人クラブ」はアメリカのAARPとは性格の異なる組織です。「定年制」などの問題は、高齢者からの働きかけがなければ解決しないと感じました。日本は「超高齢社会」と言われながら、高齢者運動は低調で、年齢差別が社会的、政治的な問題として取り上げられてすらいません。
日本の人口に占める65歳以上の割合が非常に高いというニュースも目にします。超高齢社会について、どのようなことを学びましたか?
日本ほど社会の高齢化に高い関心を持つ国は、他にないかもしれません。しかし、これは誤った関心の持ち方だと思います。それが、『超高齢社会の乗り越え方』を書いた理由の一つです。まず、私たちは「高齢化」「高齢社会」という言葉に踊らされていると思います。そうした考え方では、私たち一人一人に焦点が当てられることもなければ、人間として扱われることもありません。年齢や人口、人口構成や比率といったデータとして扱われるのです。誰一人として同じ人間はいないのに、一人一人に目を向けられることはないのです。人びとはもはや人間として扱われません。これが悲観的な将来を考えてしまう理由です。データは多様な社会のほんの一側面しか示していません。資本主義の枠組みにおいては、高齢者は生産者ではなく消費するだけの「やっかいもの」となります。
現代医療の現場においても、医師が注意を払うのは患者ではなく、検査結果だというのはしばしば耳にすることです。患者を見ずにコンピューターのディスプレイ上のデータだけを見ているとよく批判されます。ここでも同様のことが起こっています。データを見て、人を見ていないのです。検査結果を元に病気の事だけを考えていたら、ついには「病気は治せたが、患者は死んでしまった」などと言い出しかねません。
私は本の中で、これこそが「超高齢社会」という言葉がもたらす「呪文」であると指摘しました。一見、データをもとに考えているように見えますが、実際はデータに「呪文」をかけられ、関連する言葉に洗脳されているのです。「高齢化」「高齢社会」という言葉には、社会が悲観的な方向に進むことに対して何か行動しなければならないという響きがあります。言葉は私たちを操り、思考を形成し、行動を促します。問題は、頭のいい高学歴の人たちが、この「呪文」に容易にかかることです。国や地方公共団体でも、将来を真剣に考える人こそ、まっさきにこの「呪文」にかかってしまいます。それが問題です。
著書『超高齢社会の乗り越え方』では、公的介護保険制度は、大いに成功したのに、今や失敗だと評価されていると述べられています。
社会学には「予言の自己成就」という興味深い理論があります。みんなが「こうなるのではないか」と思っていると、本当にそうなり始めるのです。これは、株式市場やファッションなどの流行現象においてよく見られる現象です。小さなきっかけから始まったトレンドが、多くの人が信じることで大きくなり、みんながその通りに行動するようになるのです。介護保険に対する評価の中にも、そうしたメカニズムを見つけることができます。介護保険はそもそも、長期にわたる高齢者の介護を家族だけではなく社会が支援する「介護の社会化」という理念に基づいた画期的な政策でした。世界でも有数の高齢社会となった日本ならではの先進的な政策だったのです。社会の工業化に伴い、日本では夫婦共働き、成長した子どもは別々に暮らす核家族化が急速に進みました。そのように家族が離れて暮らす状況では、家族が高齢者の世話をすることはできません。そこで、厚生労働省は入念な検討と準備を重ね、公的介護保険制度をスタートさせました。ここまでは大きな成功と言えるでしょう。
「介護」をどう訳すのが良いでしょうか?
「介護」は日本の社会制度の中で醸成された概念であり、他の国には存在しないと思います。ですから英語でも「Kaigo」です。中国語にも存在しませんし、韓国や諸外国の言語でも同様でしょう。英語で近いのは「long term care」(長期のケア)ですが、このケアは「介護」とは異なります。介護保険という制度が提供するサービスが「介護」ですから、行政の政策用語として使われています。似たような概念や言葉は他の国々でも見られますが、日本の「介護」のケアとは異なります。介護の三つの要素は「食事介助」「排泄介助」「入浴介助」だと言われます。 例えば、日本のお風呂文化は中国と異なりますので、介助の内容も異なります。英語でナーシングホームと表現されるシステムは、看護師が長期的な介護の中心的役割を果たします。日本の「介護」で中心的役割を果たすのは看護師ではありません。介護保険制度の導入とほぼ時を同じくして、国家資格である「介護福祉士」が生まれました。介護保険制度の導入に伴い、さまざまな資格や制度が早急に設立されました。
厚生労働省の立場からすると、介護保険は医療費削減のためにも必要だったのかもしれません。医療的な必要のためではなく、世話する家族がいないなどの理由からの「社会的入院」によるコストの削減も求められていました。
従来のあり方は女性に対し、家にいて介護の役割を果たすことを求めるものでしたから、介護保険制度は多くの市民、中でも女性運動家によって歓迎され推進されました。介護を女性に押し付けることは性別役割分業に他ならず、女性の自立を大きく妨げます。つまり、介護保険制度実現の原動力は女性だったのです。また、女性の雇用を創出することもその目的のひとつでした。1980年代の市民による高齢者支援活動の多くは、女性が中心となって活動しているボランティアグループでした。1998年の「特定非営利活動促進法」によって、ボランティア団体のNPO法人化が可能になりました。女性ボランティアグループがNPO法人となり、介護保険制度のもとで介護サービス事業者となり、収入を得られることになったのです。それまでは「無償のボランティア」だったものが「有償の仕事」になったのです。 これは大きな変化でした。社会学的には、これは日本社会における性差別に対する力強い前進と捉えることができます。
しかし、政府の財政の立場からすると、これは「大いに成功したと同時に失敗でもある」のです。介護保険制度は、これまで多くの高齢者を長きにわたって支援してきました。それが政府の財政負担を重くしました。この「成功と失敗」という評価は男女の立場によって分かれます。女性の視点からは女性の負担軽減、社会的セーフティネットの提供という意味で評価されます。一方、男性からは財政圧迫や制度の持続可能性という観点から批判的に評価されます。加えて、医療、介護、福祉といった観点からの対立など、さまざまな論点があるでしょう。
日本には「姥捨山」つまり、老婆を捨てる山と名付けられた場所がまだあります。海外にも同じような習慣があるのでしょうか?
トリアージは、ナポレオン戦争時のフランス軍の医療システムとしてスタートしたとされています。負傷した兵士のうち、より早く前線に送り返すことができる見込みのある者に医療資源を集中して投入したのです。つまり、トリアージは戦争という極限状態において、限られた医療資源を最大限に活用するためのシステムとして始まったのです。これが戦争時に活用されるのは分かりますが、日常生活で運用されるとしたらどうでしょうか?明らかに非人道的です。誤って運用された場合、危険な選別方法となり得ます。コロナ禍では、年齢による命の選別が行われました。その選別はワクチン接種の優先順位付けにも使われましたが、今後どのように使われるかは分かりません。危険な考え方になりうると思います。助かる見込みの少ない高齢者が犠牲になるのは仕方がない、という選別意識につながる危険性があるのです。福祉社会学の立場から、問題提起しておきたいと思います。
『ボランティアと有償ボランティア』という著作では、NPOやボランティアの持つ可能性を再検討することで、超高齢社会への解決策を提案しています。その中で資本主義社会への解決策として、「有償ボランティア」という考え方が提示されています。
日本は今、行き詰まっています。経済は長期低迷し、世界情勢は混沌としてきました。このような状況に、経済学や政治学がどんなビジョンを提示できるでしょう。ここで社会学の出番です。政治でも経済でもない、第三の視点です。私が『21世紀の《想像の共同体》:ボランティアの原理:非営利の可能性』と『ボランティアと有償ボランティア』を書いたのは、そうした問題に対する解決策を探るためです。経済的でも政治的でもない社会学の立場から、ボランティアや非営利の持つ可能性について考えたのです。
私たちは「働く」ことによってのみ生活できると考えています。私たちはこのような「呪文」にかけられているのです。宮崎駿監督のジブリ作品『千と千尋の神隠し』で印象的なシーンのひとつに、「ここで働かせてください」というセリフがありますが、英語版ではこれは「私に仕事をください」という意味の「I want you to give me a job, please. 」と翻訳されています。このセリフは資本主義の呪文そのものです。そして物語の主人公、10歳の千尋は、グローバル資本主義のような湯屋での奴隷労働に放り込まれます。働くことが「労働」ではなかった生き方を私たちは取り戻さねばなりません。ですから「無報酬のボランティア活動」だけではなく「有償のボランティア活動」もありうることを述べました。すでにアメリカでは普通に実現していることです。日本でも、そこから「労働ではない仕事」が生まれてくるのではないかと論じたのです。それはボランティア団体にとどまらずNPO法人という新しい「想像の共同体」を生み出します。そこから「労働を超える仕事」も生まれてくるのではないでしょうか。
映画『千と千尋の神隠し』では、主人公の千尋は、もうひとりの魔女の銭婆婆に会うことで呪文を解きました。湯婆婆との最後の対決では、何匹もの豚の中から豚にされた両親を見つけることができたら解放してやる、という挑戦を受けます。千尋はその中に両親がいないことに気付きます。示された選択肢の中に「正解」はない、という「答え」をみつけたのです。こうして湯屋での奴隷労働から解放された千尋は、さらに思いもよらない行動にでるのですが、それは次の本で詳しく書きました。
2023年3月に出版した新刊『福祉の起原』(弦書房)では、戦争と福祉について考えています。厳しい財政を理由に福祉が縮小されているのに、どうして戦争は起こるのでしょうか。福祉が立ち行かなくなる一方で、戦争が起こる可能性はもっともっと高まっています。単純に考えて理屈の通らないことですが、今、世界はその方向に向かっています。私たちは「呪文」に捉われているとしか思えません。悪夢に向かう予言の自己成就のプロセスに捉われてしまうことが、こうした「呪文」の危険性なのです。
福祉は自然に生まれたものではありません。善意や慈善事業から自然に発展したのではないのです。戦争があったから生まれたと考えられます。戦争のもたらす破壊や悲劇が福祉の必要性を生み出したのです。20世紀の「福祉国家」は、第二次世界大戦後に誕生しました。戦前の日本に「福祉」はありませんでした。宗教的な慈善や、国家による選別的な施しのようなものはあったかもしれませんが、普遍的な人権思想にもとづく「福祉」はありませんでした。日本の敗戦後、連合国軍総司令部(GHQ)は、日本のファシズムが社会問題の解決能力の欠如から発生したと分析して、日本政府に対し、アメリカの社会保障法をモデルとして国民を援助するよう指示しました。それに対して日本政府は「生活保護法」を作りました。そこには不思議なねじれもありますが、いずれにせよ「福祉」は内から自然に現れたものではないのです。
観衆の裾野を広げるジブリの世界に基づき、社会学の考え方を論じていますね。
40歳以下のほとんどの方がジブリ映画を鑑賞したことがあることから、講義や学術書で引用しています。ジブリ作品を引用することで、社会学的な思考を身近で具体的なものとして感じられるようになり、私たちの生活における問題との接点を見出すことができるのです。キャラクターやストーリーについて考察することが、社会学と現実の世界をつなぐ架け橋になるのです。
26年前に九州大学に着任したとき、社会学は文学部に所属していました。いまは人間環境学研究院に所属して社会科学のひとつと考えられています。しかしながら、文学や哲学、それに経験科学の性質を併せ持つことは社会学の大きな強みなのです。社会学者の見田宗介氏のアプローチがその一例です。事実のデータだけでなく、人々の暮らしのリアリティをたいへん重視しました。見田宗介氏は『まなざしの地獄』という本でひとりの殺人犯の人生を追いかけて、当時の地方出身者の人生のドラマと、戦後の高度成長期の日本社会の病理とをみごとに浮き上がらせました。見田さんは、流行歌に現れる社会心理や、新聞の人生相談などからも、人間の心理と社会学との見事な融合が可能であることを示しました。私もこうした方法論を、これからも冒険心を持って実践していきたいと思っています。