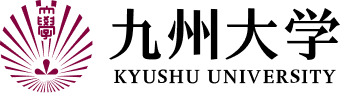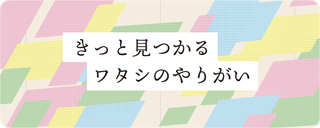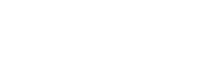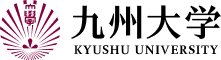-
カテゴリ別
-
場所
-
最新のお知らせ 年間スケジュール(就職対策講座等) OB・OG情報 システムの利用方法 学内合同企業説明会(「九州大学生のための業界・企業研究」) 学内企業研究セミナー / 個別企業説明会 公務員・教員等採用情報 就職相談 就職情報室 キャリア教育 低年次学年向け情報 インターンシップ等(学生向け) TOEIC対策プログラム 博士人材のための就職支援(学生向け) 外国人留学生のための就職支援 未内定の学生及び既卒者(卒業後3年以内)の皆様へ 障害のある学生のための就職支援 部局独自の就職支援 東京・大阪・博多駅オフィスの利用 各種情報サイト 過去の就職状況 採用選考に関する指針 学内合同企業説明会 博士人材のための企業説明会(企業向け) 本学へのご訪問 求人情報ご提供 OB・OG名簿ご提供 インターンシップ等(企業向け) 外国人留学生の採用 採用選考に関する指針 就職担当 よくあるご質問
Research Results 研究成果
 2024年能登半島地震の約3時間後より発生した南海トラフのスロー地震活動を分布型音響センシング(DAS)によって観測
2024年能登半島地震の約3時間後より発生した南海トラフのスロー地震活動を分布型音響センシング(DAS)によって観測
理学研究院
馬場 慧 助教
2025.12.12研究成果Environment & Sustainability
ポイント
- 南海トラフでは、光ファイバーケーブルを用いた分布型音響センシング(DAS)による連続観測を行なっている。
- 2024年の能登半島地震の約3時間後より、南海トラフで発生する小規模な微動活動をDASによって観測できた。
- 大地震後の地震・スロー地震活動を詳細にモニタリングするために、DASの連続観測は有効である。
概要
巨大地震が発生する南海トラフの沈み込み帯では、通常の地震のほかに、スロー地震(※1)とよばれる、通常の地震よりもゆっくりとした断層すべり現象が起こっています。スロー地震は、巨大地震との関連も示唆されている現象で、その活動の実態や発生メカニズムを明らかにすることは重要です。スロー地震は、離れたところで発生した大地震による応力変化の影響を受けて活発化することが知られており、このような誘発現象の知見は、スロー地震の発生メカニズムを考えるうえで鍵となる示唆を与えます。
南海トラフに面した室戸岬の沖合では、海底ケーブルによる分布型音響センシング(DAS)(※2)による連続観測を行なっています。DASは、光ファイバーケーブルに沿った歪の変化を計測するもので、数m〜数十mおきという密な観測が可能であることから、新しい地震観測方法として注目されています。
九州大学大学院理学研究院の馬場慧助教、海洋研究開発機構の荒木英一郎グループリーダーと堀高峰センター長の研究グループは、2024年1月1日16時10分に発生した能登半島地震後の、室戸岬沖のDAS観測のデータを注視していたところ、本震の約3時間後から、小規模なスロー地震活動が起こっていることがわかりました。これらのスロー地震は、南海トラフのスロー地震発生域の西端で起こっており、能登半島地震による応力変化によって引き起こされたものと考えています。能登半島地震の影響を受けて、海底地震計の一部は十分な観測ができていなかったため、この活動はDASの連続観測を行なっていなければ検出できなかった可能性があります。この研究はDASの連続観測を続けていたからこそ行えたもので、大地震後の地震・スロー地震活動をモニタリングするためにDAS観測は有効であることが分かります。
本研究成果は、米国の雑誌「Geophysical Research Letters」に2025年11月25日に掲載されました。
研究者からひとこと
この度DASで観測できたスロー地震活動は、小規模なものではありますが、約600 km離れた能登半島地震の発生後に起こったもので、大地震後のスロー地震活動の発生メカニズムという観点で、重要な活動であったと考えられます。この活動は、DASの連続観測を行なっていなければ見つからなかった可能性があり、DAS観測の重要性が示されたと考えております。
図1 本研究でDAS観測を行なっている領域(緑色の線がDAS観測に使用したケーブルを示す。四角形は、海底地震観測網DONETの観測点の位置を示す。灰色・赤色の丸や星印は、先行研究(Takemura et al., 2022; Tamaribuchi et al., 2022; Baba et al., 2023)のスロー地震の震源を示す。)
用語解説
(※1) スロー地震
通常の地震よりもゆっくりとしたすべりで、主に沈み込み帯の巨大地震の大すべり域周辺で観測される。南海トラフでは、沈み込むフィリピン海プレートと上盤のユーラシアプレートの境界の、巨大地震の大すべり域の浅い側(海側)と深い側(陸側)で発生しており、それぞれ浅部スロー地震と深部スロー地震と呼ばれる。スロー地震は特徴的な時間スケールによっていくつかの現象に分類され、スロースリップイベント(数日〜数年)、超低周波地震(20–50秒)微動(0.1–0.5秒)といった現象がある。
(※2) 分布型音響センシング(DAS)
光ファイバケーブルにレーザー光を入射し、返ってくる光の位相の変化から、ケーブルに沿った歪の変化を数m間隔で計測できる観測技術。従来の地震計よりも稠密な観測が可能であることから、近年、地震観測や構造探査に用いられている。
論文情報
掲載誌:Geophysical Research Letters
タイトル:Shallow tremors near the Nankai Trough activated after the M 7.6 Noto Peninsula earthquake
著者名:Satoru Baba, Eiichiro Araki, Takane Hori
DOI:10.1029/2025GL118973
- 本件の詳細はこちら
お問い合わせ先